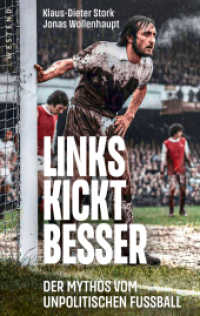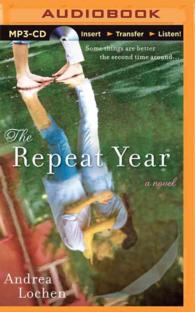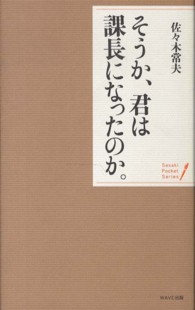出版社内容情報
【内容】
どのように工夫すれば学生が頭を使ってレポート課題に取り組むのか?これまで理論的には問われてこなかったこの問いに、「レポート論題」、「授業設計」、「評価」の各観点から答える渾身の書。特に「剽窃が困難となる論題」についての分析は、これまでのレポート課題のあり方を根本から問い直す。
執筆者:成瀬尚志、河野哲也、石井英真、笠木雅史、児島功和、髙橋亮介、片山悠樹、崎山直樹、井頭昌彦
【目次】
はじめに
第1章 なぜレポート課題について考えるのか
1 レポート課題で何を問うべきか
2 学術論文と学部レベルのレポート課題の評価の違い
3 レポート課題から授業を設計することの意義
4 授業設計においてレポート課題はボトルネック
5 ネット時代においてレポート課題で何を問うべきか
第2章 論証型レポートについて考える
目次
第1章 なぜレポート課題について考えるのか
第2章 論証型レポートについて考える
第3章 レポート論題の設計―剽窃が困難となる論題分析
第4章 レポート課題を軸とした授業設計
第5章 学生が自分で問いを立てるための授業デザイン
第6章 レポート課題を評価するとき―ルーブリックの活用
著者等紹介
成瀬尚志[ナルセタカシ]
京都光華女子大学短期大学部講師。専門は哲学、高等教育。神戸大学大学院文化学研究科単位取得退学。博士(学術)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobuko Hashimoto
27
大学でのレポート課題において剽窃が問題になっているが、罪を暴くという性悪説的な発想ではなく、剽窃しようがなく、自分の頭を使わないとできなくて、やりがいを感じることのできる出題にすべしという観点から、大学教員に向けて書かれた本。出題の仕方、レポート作成へ向けての指導のあり方などが丁寧に整理されていて勉強になる。授業方針や授業の流れ、評価の考え方など、おおいに同意、共感できた。本全体としては、学期、一年、4年通しての指導の実例研究があるとさらに参考になると思う。2022/03/06
しんえい
9
授業においても論証型レポートは書かせていたが、探究学習が必履修化される今後はますます論証型レポートが必要になるのでは。反論はその根拠・論拠を反論するべき(p25)とあり、その方法について生徒たちにもなるべく具体的に技能として指導したい気もする。教育における評価(p154)のうち、教育現場は「学習のための評価」「学習としての評価」にもっと目を向けるべきだと思った。パフォーマンス課題等に対して生徒自身が自己・相互評価できる学習活動を取り入れてみるのはどうか。2020/07/24
ぽっか
7
大学教員に向けて書かれた本で、レポート課題を出すときにどのような指導をすればいいかが丁寧に解説されている。剽窃がだめなのはもちろんだけど、では教員は剽窃をふせぐような課題が出せているか、指導ができているか、その課題でいったい何を評価したいのか。提出物の完成度よりも、学生が自分で文章を評価するものさしを持てたかどうかに注目したい、という指摘にすごく納得。大学教員向けだけどアクティブラーニングが主流になって来つつある(?)今、小中高の先生にとってもヒントがたくさんありそう。ルーブリックの理念もよくわかった。2019/03/31
虎哲
6
科研費研究メンバー、公開研究会のゲストの寄稿からなる「レポート課題を軸に考える授業設計マニュアル」。去年の全国大学国語教育学会茨城大会で買って適宜参照しつつも通読できていなかったが、クロゾフさんが通読、推奨されていたこともあり、時間を作って一気に読んだ。「良い論題を出せば、良いレポートが生まれる」という「暗黙の前提」は私の少ない経験からも同意できるものだが、その論題をどうするか、授業をどう設計するかが重要だ。72頁に示されたRタキソノミー、「自分の中のものさしを成長させる」授業設計を今後も念頭に置きたい。2020/07/09
Bevel
3
コピペを生まない良いレポートの題とは何かということで、一般的に取り入れられがちな論証型レポートの有効性に疑いの目を向けてみるという感じ。全体として、やはり学生のアウトプットの機会をできるかぎり増やすのがよいのだろうと感じた。人文系の能力ってぱっとイメージしてもらえないことが多いため、ルーブリックとして最初に説明するのもうまく取り入れてみたい。2021/01/18