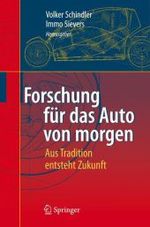- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
目次
逸脱者と近代的権力
第1部 「変態」の生成と流動(変態性欲論と変態心理学―大正期「変態」概念の成立;「変態」に懸ける―『変態心理』読者とそのモチベーション;「民衆」からの“逸脱”―「変態」概念および天才論の流行と文壇人 ほか)
第2部 「変態」と呼ばれた者たちの生(共同体への憧憬―小山内薫の芸術観と大本教信仰;欲望される“天才”―「変態」概念による批評と有島武郎の“偶像”化;主体化を希求する“逸脱者”たち―男性同性愛者たちの雑誌投書)
第3部 「変態」の“商品”化―エロ・グロ・ナンセンスの時代(エログロへの“転向”―梅原北明の抵抗と戦術;左翼・エログロ・ジャーナリズム―『新愛知』におけるプロレタリア文学評論とモダニズム;プロレタリア文学の“臨界”へ―井東憲『上海夜話』におけるプロレタリア探偵小説の試み)
“逸脱”・共同体・アイデンティティ
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
∃.狂茶党
7
ラヴクラフトとヒトラーが夢見る少年だった頃。 クラフト・エピングの研究は、正常とされるものから逸脱したとされるものに、劣等なイメージを植え付けた。 これは、進化論の衝撃とともに、退化した人を描き出す。 逸脱を進化や適応に結びつけぬことは、この頃成熟してきた、国家主義や民族主義と結びついたものだろう。 性的逸脱とともに、心霊もまた、西洋化・近代化される。 だからこれは、ファシズムの見る世界なのかもしれない。2022/08/18
つまみ食い
4
秀逸な戦前日本の文化論。科学的な言説として立ち現れた「変態」概念が次第に科学色を薄め、文化消費の対象となっていくプロセスを描きだす2022/12/08
ア
2
1910年代に日本社会に浸透した「変態」概念の発生と展開を、その「消費」に焦点を当てながら分析する。相当面白かった。「変態」概念による主体化という点など、表象による抑圧ばかりが強調される中で、重要な指摘に思う。いわゆるエロ・グロ・ナンセンスは十五年戦争を境に勢力を落としてしまう。筆者は「変態」の流行を支えた人々の〈小さな革命〉への欲望が、国家主義的な共同幻想の中で変容してしまったのだと結論付けている。それならば、占領期に花開いたカストリ文化は戦前の「変態」とは無縁のものなのだろうか2019/01/13
Erina Oka
0
再読。2014/08/18
-
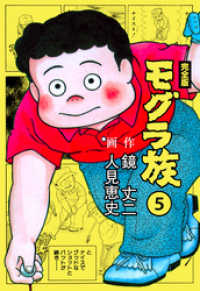
- 電子書籍
- モグラ族【完全版】5 マンガの金字塔
-
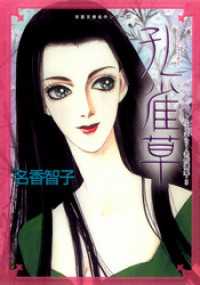
- 電子書籍
- 名香智子ミステリー選集(3) 孔雀草 …