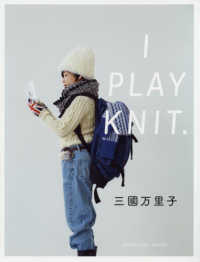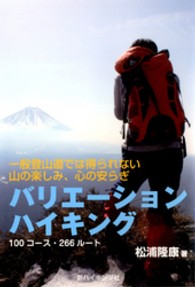目次
電子化によって書物/文学とそのディスクールおよび受容にどんな変化が生じるのか
名作は誰のもの?―アメリカの読み捨て本VS.明治文学の金字塔
国際金融とネット言論の倫理―メタレベルなき世界での合意形成をめぐって
フェティシズムの現代的意義―岡川氏の論文の補足と若干の私見
歴史を記述する倫理―近年における「史料改変問題」を事例に
書くことの公共性はいかにして成り立つのか―カントの再読を通して
逸脱という戦略―谷崎潤一郎『悪魔』『続悪魔』における主体の生成
3・11以降に語ること―単独であるところから、古典知と共に
文字を何に載せるかということ―ある戯作への自注
著者等紹介
助川幸逸郎[スケガワコウイチロウ]
横浜市立大学他非常勤講師
堀啓子[ホリケイコ]
東海大学文学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
歩月るな
3
10年前の2010年のシンポジウムを基にした論文が収められてる本だが、3.11以降に触れた言説が光る。報道に対する「ネット言論の道徳」に触れていたり、市場の為替取引をパロールとラングに言い換えた表現がなかなか面白い。タイトルは<語ること>だが、<描かれたもの>も同様のコミュニケーション手段なのは見ての通りである。10年で何が変わっているか考えてみるのも良いかもしれない。『小説神髄』以降の翻案小説の広がりが文学の土壌なので、著作権云々も然り。カント読みたくなる。10年前とは言え今現在も変わってないような。2020/05/21