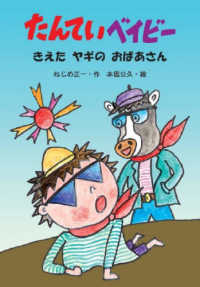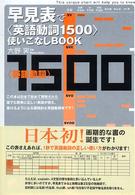出版社内容情報
ピアとは仲間、同僚(peer)という意味の言葉。ピア・ラーニングとは、近年、いろいろなところで耳にするようになっている「協働」の理念に基づく学習である。本書では、まず、理論編として、地域や学校などさまざまな分野で 具現化された協働の形を紹介したうえで、日本語教育における協働のありかたをさぐる。実践編として、ピア・レスポンスおよびピア・リーディングの具体的な学習活動の例について紹介、解説し、その意義について検討する。
目次
第1章 協働とは(協働の定義;市民協働の原点 ほか)
第2章 さまざまな協働の学び(対話的問題提起学習;シナゴジー理論による相教学習 ほか)
第3章 ピア・ラーニングとは(学習観の転換と協働の背景;ピア・ラーニング ほか)
第4章 ピア・レスポンス(ピア・レスポンスとは;協働学習としてのピア・レスポンス ほか)
第5章 ピア・リーディング(読解授業の問題点;ピア・リーディングのはじまり―なぜピア・リーディングなのか ほか)
著者等紹介
池田玲子[イケダレイコ]
東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科教授。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(人文科学)。専門は日本語教育学、日本語表現法。小、中、高等学校の教員を経て、拓殖大学日本語センターの日本語教師、お茶の水女子大学文教育学部では日本語教育と日本語教師養成に携わる。2004年より現職
舘岡洋子[タテオカヨウコ]
早稲田大学大学院日本語教育研究科教授。早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。専門は日本語教育学、言語教育学、教育心理学。1987年よりアメリカ・カナダ大学連合日本研究センター、2001年より東海大学留学生教育センターを経て、2007年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
るん
aoi
宵子
よっちん
みんみん
-
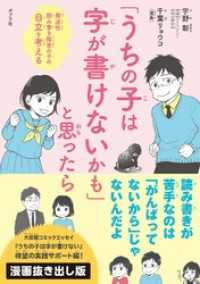
- 電子書籍
- 「うちの子は字が書けないかも」と思った…
-

- 和書
- 恋か殉死か!