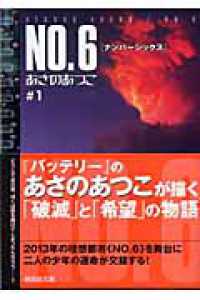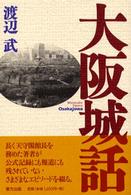内容説明
一七世紀後半から日本各地で海岸林づくりが本格化する。海辺に住む人々は木を植えて飛砂から耕地や家屋を守らなければならなかったからである。海岸林の主林木として塩害に強いクロマツが選ばれた。砂丘が人々に脅威を与えるまでに拡大・荒廃するにはさまざまな要因があるが、長期にわたる森林破壊や急激な新田開発を無視することはできない。砂丘は内陸の土砂が河川をへて海に流れ込み、それが浜に打ち上げられ風に運ばれて形成されるが、人間による地形の改変によって過剰な土砂が川にもたらされたのである。本書は、飛砂の猛威と格闘した有名無名の人々を紹介しながら、マツと人とのつき合いを古代までさかのぼり、考古学、文学、絵画、景観論などの成果を幅広く取り入れて考察する。また、三大白砂青松や三大松原の地を歩き、人々が海岸林の美しさを「白砂青松」という言葉によって表現するようになった背景を考えている。
目次
第1章 砂丘の成り立ち
第2章 海岸砂丘にはいつマツ林が成立したか
第3章 マツは砂丘へ侵入する
第4章 人とマツのかかわり
第5章 拡大する砂丘
第6章 荒廃した砂丘
第7章 砂丘にマツ林をつくる
第8章 マツ林のはたらき
第9章 白砂青松の成立
第10章 三大白砂青松と三大松原
第11章 現在の問題
著者等紹介
小田隆則[オダタカノリ]
1947年、長崎県生まれ。2002年、没。東京大学農学部卒。農学博士(戦後初めて、海岸林の生態・造林部門で学位を受けた)。日本海岸林学会評議員、千葉県森林研究センター主任研究員として海岸林や海岸砂丘の研究に携わる。作家として、相馬隆のペンネームで「第10回小説推理新人賞」(1988年)を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。