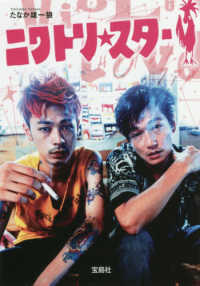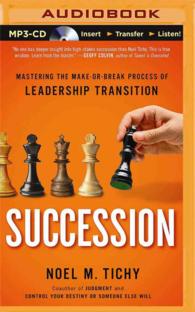目次
はじめに―違和感を出発点に考える
1 保育の場で君が代を歌わなければならないの?
2 日の丸・君が代をめぐって学校現場で起きたこと
3 国旗や国歌のはたらきってなんだろう?
4 幼児が育つ場で日の丸を掲げ、君が代を歌わせるのはどんな教育だろうか?
5 幼児が育つ場としてふさわしい環境とは何かという視点から考えてみる
6 国はなぜいま日の丸・君が代を保育現場に持ちこもうとしているのか
おわりに―保育の場で譲ってはならないこと
著者等紹介
中西新太郎[ナカニシシンタロウ]
1948年生まれ。横浜市立大学名誉教授。専攻は社会哲学、現代日本社会論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
25
保育現場に日の丸・君が代を親しむことが保育所保育指針などで示されました。幼児期の子どもたちに日の丸・君が代は本当に必要なのかを考えることができる内容です。親しむとありますが、子どもが自ら遊びの展開のなかで親しむのではなく、大人が決める徳目や意図のなかで親しむことが求められます。森友学園の幼稚園の教育勅語暗唱などの映像はとても違和感を覚えましたが、それと同様なことが保育現場に押し付けられていくのではないかという危惧を持ちました。子どもが主体的に考える発達段階はあると思います。それも無視したものだと思います。2017/07/03
たく○
0
著者に聞いてみたいのは、例えば「園歌を歌わない」「何で園歌を歌わなければいけないの?」という子がいた場合、どう対応するのかということだ。子どもが自分自身で考えること、主体的に考えることは大切だ。しかし、保育現場に君が代を持ち込むことで、子どもの主体性が奪われる危険があるというのは、少々議論が乱暴だ。どんな歌でも、無理やり歌わせるのであれば、それが園歌や童謡であっても同じだ。結局のところ大切なのは、保育者がどのように接するか、ということだ。子どもの主体性や社会性の発達について、あらためて考えることができた。2017/10/09
-
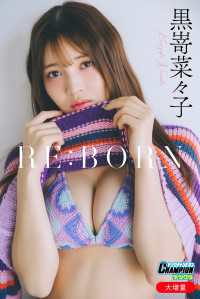
- 電子書籍
- 黒嵜菜々子「【大増量】RE:BORN」…