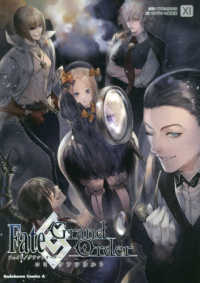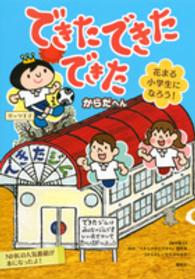内容説明
子どもの行為がついつい否定的に見えてしまうのはなぜ?やっぱり「できる、できない」が気にかかるのは?世界は今、保育・幼児教育観の転換の時を迎えている。新しい子ども観・発達観を内包した「学びの物語」を実践すると、それまでとはまったく違う子どもの姿が立ち現れる。
目次
第1章 子ども観転換の時代を生きる(「準備期としての子ども」から「ひとりの市民としての子ども」へ;「子ども」を見る新しい視点―発達への社会文化的アプローチとは;子ども観が変わると保育実践が変わる;実践を変えるために、子どもの「評価¥理解の方法」を作りかえる)
第2章 「学びの物語」の保育実践(「学びの物語」のススメ;「困難に立ち向かっている」姿が見えてくる時;「関心」と「熱中」からどのようにしてチャレンジが生まれるか;子どもの関心とはどのようなものか;自分の考えを表現することと自らの責任を担うこと)
第3章 「学びの物語」で保育の質を高める(質をめぐる今日的争点―「保育の成果」をどうとらえるか;「学びの物語」は子どもの発達をどのようにとらえるものなのか;学びの物語における「子ども理解」の特質;「学びの物語」と保育の質)
第4章 保育理論としてのテ・ファリキ―その子どもの見方・とらえ方とは(「原理」と「領域」の糸で織り上げられた「テ・ファリキ」;めざす人間像と五つの「領域」;学び。成長するために必要な権限を子どもたちに;子どもは「関心と意味」に導かれて発達する;子どもは、この社会を、私たちとともに生き、考えている;子どもの成長には「応答的で対等な関係」がなくてはならない)
著者等紹介
大宮勇雄[オオミヤイサオ]
1953年福島県生まれ。東京大学教育学研究科修了。現在、福島大学人間発達文化学類教授(幼児教育)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。