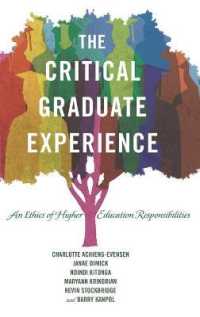目次
1 目の前の子どもの姿から保育を変えていく―五歳児クラスの二年間から学ぶ(一年間、年長組の保育を園内学習のテーマに;恒例の年長最後の行事をとりやめるまで)
2 実践しながら子どもの思いをつかみ手だてを見いだす―三歳児・二歳児クラスの子どもと保育者たち(子どもたちととことんあそび続けることで発見したこと;悩みつつ揺れつつ子どものことを語り続ける)
3 わかってもらえたと子ども自身が思えるまで―子どもたちの五年間の育ちと保育を記録から読みとる(卒園する頃の子どもたち;一歳児クラス(ひよこぐみ)でしずかちゃんを気にする ほか)
4 小宮山先生が学んだこと・小宮山先生を通して学んだこと(はじめて担任したあさみちゃんとの格闘;なぜ、年長の子どものことで学習会するの?私の保育に問題が? ほか)
5 「子どもの側に立つことを徹底する」を深める(「子どもをわかろうとすることに徹する」とはどういうことか―観察者としてではなく、かかわるなかでわかろうとする実践者としての子ども理解;「子どもの側に立つことを徹底すること」と「どこまで子どもの要求を受けとめていいのか?」という問いかけの違いを考える;子どもをわかることから出発して、どこに向かうのか;「徹底して子どもの側に立つ」保育を可能にする職場のあり方)
著者等紹介
清水玲子[シミズレイコ]
1947年、埼玉県に生まれる。東洋大学ライフデザイン学部教授。乳児保育、保育原理などを担当。子ども二人は産休明けから共同保育所を出発点に、公立保育所、共同の学童保育で育つ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Takao
-

- 和書
- 生体機能の見方