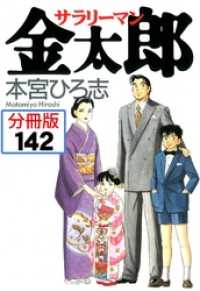内容説明
親子でチャレンジ、今、大ブレーク中の「光る泥だんご」。
目次
1 光る泥だんごの作り方―改訂版
2 トラブルシューティング―初中級法用
3 なぜ泥だんごは光るのか―出会いと謎の解明
4 作ってみました(やっぱり基本は泥だんご―保育園幼児クラス;泥だんごは面白い―学童;スベスベプリン―保育園乳児クラス;名人の一言)
著者等紹介
加用文男[カヨウフミオ]
京都市・京都教育大学教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
書の旅人
10
『光れ!泥だんご』を買ったのは、もう忘れてしまうくらい前でした。自然の中で暮らしたいと夢を描き、とにかく幅広く情報が欲しくて、新聞や雑誌を切り抜き、関連本を探しては読み漁ってました。一度は諦めた夢ですが、“縁”はやはり、“円”。ちゃんと繋がっていたのですね。この本を見つけた時、また夢のかけらが、戻ってきました。今度は、ポレポレの丘の子どもたちと一緒に作りたいです。みんなそれぞれの、個性溢れるだんごを見たいです。2017/10/10
坂津
1
『光れ!泥だんご 普通の土でのつくりかた』と同じく、小学生の時に図書館で繰り返し読んだ本。前述の本は子供でも絵本感覚で読めるのに対し、本書は子供に付き合って一緒に泥だんご作りに励む保護者目線の視線で執筆されている。子供の頃は、主として泥だんご作りに言及される前半部分と、後半で紹介される「ツルツルプリン(泥だんごの亜種)」の箇所ばかり読んでいたが、大人になって通読してみると、編者(京都教育大学教授)が泥だんご作りにハマったきっかけを綴ったエッセイや、そのきっかけを与えた幼稚園教諭の語りが印象に残った。2023/09/17
どりたま
1
「たかが泥だんご、されど泥だんご」。なかなか奥の深いものだと思いました。今まで光る泥だんごは聞いたことも見たこともありませんでしたが、子供と泥だんごを作っているときに通りかかったご年配の人たちから聞いて興味を持ち、この本を見つけました。読んだら、作るしかないでしょう!この本は作り方だけでなく、著者の泥だんごとの格闘談や名人の一言など泥だんご話に深みを与えてくれます。2013/06/15
npu
0
トラブルシューティングとして活用出来そう。2010/04/24
星雅人
0
★★★☆☆ わかるんだけど、実際にそこまでのが作れないんです・・・。研究あるのみ。2009/04/07



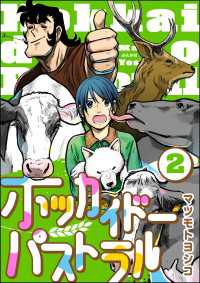
![good!アフタヌーン 2020年1号 [2019年12月7日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0796385.jpg)