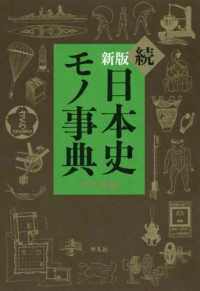内容説明
森の王者の最新情報、私たちが知っておくべきこと。ネーチャーマガジンモーリー49号、50号掲載のヒグマ特集を1冊に再構成。
目次
ヒグマはどれほど危険な動物なのか?
ただ駆除を続けても出没は減らない
札幌のヒグマとどうつきあうか
さあどうする、あなたの街にもクマは出る
電気柵はどのくらい有効か
利尻島のヒグマ駆動から何を学ぶか
ヒグマ調査のクマ対策
知床半島のヒグマの現状
広域移動するヒグマから見えてきたもの
森の中で恋の相手やライバルをどう見つけるのか
軽井沢とベアドッグ
文学作品に登場する羆
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
39
北海道新聞社がまとめたヒグマとの共存を探る本です。基礎知識から歴史、遭遇の可能性がある状況などが考察されていて、勉強になりますが、同時に出没率と事件の関係性などのデータがあるならまとめたものを見たいなあ…と思いました。World Animal Foundationのデータによると、世界で一番人を襲うクマはヒグマ(Brown Bear)だそうですが、クマのメッカのように言われるイエローストーンでは1872年から2022年現在まで、クマに殺された人は8人のみ(しかもハイイログマ)なようです。読み友さんから。2023/04/14
アッキ@道央民
29
北海道新聞社発刊。ヒグマとの共生をテ-マにまとめられた1冊。酪農学園大学や北大などのヒグマの研究者や知床財団の職員の方等によるヒグマ問題に関する記述は興味深いものがある。今年は本当、札幌含む道内の至る所でヒグマが目撃。山間部近くとは言っても住宅街のすぐ側でもヒグマの出没が相次いでいますが、ここ数年の出没状況を見てみると、今に始まった事ではないんだなとわかる。好む好まざるに関わらずヒグマは身近な野生動物。正しくヒグマの事を理解して正しく恐れたいものです。ヒグマの基本的な生態や糞や食痕等も紹介されています。2023/07/05
spatz
16
図書館のカウンター横に、小さなコーナーがあり、そこに、北海道のヒグマ関連の本、マタギ、などの本と一緒に置かれていた。 ヒグマをテーマに書かれた別の本と感想の大半はおんなじ。(つまり一般論として) 説得力のレベルが違う。 この本は「ヒグマとの共生を目座す」人たちによって編まれている。 目次を示したが、ヒグマについてのフィールドワークを重ね、研究を重ねてきた人々がいる。害獣だから駆除という短絡的な考えではない。 利尻島のヒグマ騒動、軽井沢のベアドッグの話なども。2022/12/18
みろみ
3
図書館本。北海道に住んで48年、キツネとエゾシカは家の近所にもいますがさすがにヒグマに出会ったことはない。保護もわかりますが、家の近くに出たら駆除して欲しくなるよなぁ。2019/10/05
リアム
2
人間がいる暮らしに適応してきたヒグマと様々な警鐘に対し生活改善ができない人間。2019/05/18
-

- 電子書籍
- 幼い皇后様【タテヨミ】第98話 pic…



![レゴアニマルアトラス [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/44878/4487811759.jpg)