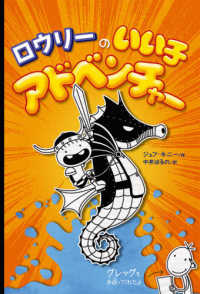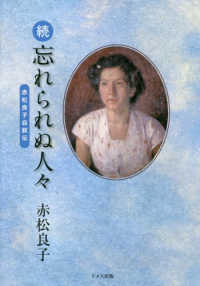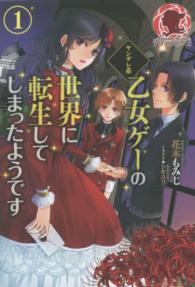内容説明
支配層であった満洲人の満洲語、そしてモンゴル語、漢語の三言語を公用語とした「大清」。独自の「八旗」制度などの統治システムで広大な国土を領した大清帝国(1636~1912)の全体像を、チベット、ロシア、ヨーロッパはじめユーラシア全土との関わりの中で明らかにする。
目次
1 清朝とは何か(大清帝国にいたる中国史概説―十三世紀に成立したモンゴル帝国から、大清帝国への流れをたどる;世界史のなかの大清帝国―世界史はモンゴル帝国から始まった;マンジュ国から大清帝国へ(その勃興と展開)―満洲の地域国家からユーラシア東方の世界帝国への歩み ほか)
2 清朝の支配体制(大清帝国の支配構造(マンジュ(満洲)王朝としての)―八旗制度を中核とする帝国統治のシステムをさぐる
「民族」の視点からみた大清帝国(清朝の帝国統治と蒙古・漢軍の旗人)―「多民族」混合の政権としての清朝の特徴とは?
大清帝国とジューンガル帝国―清朝が滅ぼした、モンゴル系遊牧民最後の帝国ジューンガルとは? ほか)
3 支配体制の外側から見た清朝(「近世化」論と清朝―十六~十七世紀の世界諸地域での「近世化」における清朝の位置は?;江戸時代知識人が理解した清朝―輸入漢籍を通して江戸時代の日本人が考えた清朝とは?;琉球から見た清朝(明清交替、三藩の乱、そして太平天国の乱)―明から清への交替期、琉球王国はどのように対応したか? ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なつきネコ@着物ネコ
15
大学のレポートのためのだったがおもしろい。清朝と周りの国、もしくは自国内の多民族との関係から見る清朝史という内容だった。よく、満州民族はあの中国をよく纏められたか、驚嘆する。あまり、知らないチベットのダライ・ラマとの共生は興味深く、同じモンゴルを継いだジューンガルとの攻防、ロシアとの関係など本当に他国との関係は興味深い。最後の満州帝国の記事は本当に攻めた内容だった。美化しない韓国、ロシア、満州、漢民族、日本の近現代史は納得がいく。本当にこの時期はロシアの動向を考えないと極東史はわからなくなってしまう。2023/03/31
(ま)
1
断代史で中国史を語ること勿れ2019/03/22
Teo
1
別冊環である事から、複数人の寄稿になり重複する部分が多いのは避けられない。八旗の件などは特にそうだ。みどころは最後にある宮脇淳子の「大清帝国と満洲帝国」。PHP新書の「世界史のなかの満洲帝国」では控えめだった筆致がかなり言いたい事を書いていると思う。2009/06/14