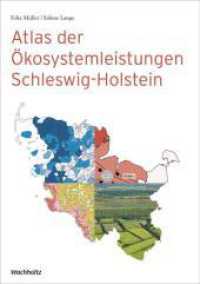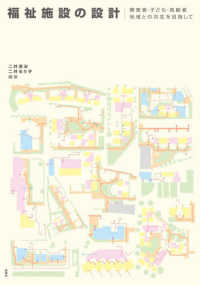内容説明
日本舞踊の名取として自らも舞台に立った鶴見和子が、国際的舞踊家二人をゲストに語る、初の「おどり」論。伝統、「型」、「間」など舞踊の本質に迫る深い洞察、武原はん・井上八千代ら巨匠への敬愛に満ちた批評―おどり手かつ観客として「おどり」への愛情とその魅力を存分に語り尽す。
目次
第1部 鼎談 おどりとは何か(私のおどり;海外公演の経験―花柳寿々紫;海外公演の経験―西川千麗;日本のおどり、西洋のおどり;武原はんと井上八千代;おどりと自然環境;人間にとって、おどりとは何か)
第2部 対談 おどりは人生(おどりに言葉はいらない;古典と創作;「日本舞踊」とは)
著者等紹介
鶴見和子[ツルミカズコ]
1918年、東京生まれ。比較社会学専攻。幼少より初代花柳徳太郎門下でおどりを、佐佐木信綱門下で短歌を習う。21歳で花柳徳和子を名取。津田英学塾卒業後、41年ヴァッサー大学哲学修士号取得。ブリティッシュ・コロンビア大学助教授をつとめたのち、66年にプリンストン大学社会学博士号を取得。69年上智大学外国語学部教授、同大学国際関係研究所所員(69~89年。82~84年同所長)を経て、89年定年退職。上智大学名誉教授。95年に南方熊楠賞受賞。1999年度朝日賞受賞
西川千麗[ニシカワセンレイ]
舞踊家
花柳寿々紫[ハナヤギスズシ]
舞踊家
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 死に戻り花嫁の2度目の結婚生活~離婚宣…
-

- 電子書籍
- 死にかけ悪役令嬢の失踪~改心しても無駄…