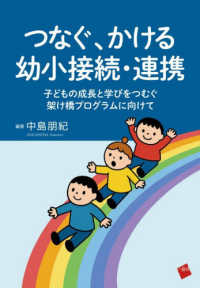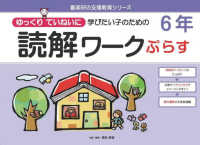- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
10
原題はSur la télévision(1996)。本書はテレビ、ジャーナリズム、視聴者の関係を他の界との力関係において記述する。情報を見せることで隠し、紋切り型の言説を振り撒き、視聴者が数値化される商業主義的なテレビという界は、競争的な情報市場にあるジャーナリズムの支配力を背景に「ファスト・スィンキング」と「プロレス」的議論ゲームを氾濫させる。一方視聴者は、他の界(大学界や歴史学者の界等)の思考を難解か劣ったものと枠づけられ(凡庸化、均質化、脱政治化)、その枠内で情報を欲望する循環の中にあるとされる。2024/05/21
tooka
2
メディア批判する人は必見。意訳をひとつ。ランキングは本来数字を集計しただけのもので、評判を計るひとつの指標であるだけにもかかわらず、突出した発言力をもってしまう(読者の軍資金が人気作家に集中する結果、新人作家の売り上げに困難が伴う)。不釣り合いな力を持った数字はしばしば利用され(ランキングの操作)、ますます虚構の声に本当の声はかき消されていく。2009/12/18
momonori
1
ブルデューが一九九六年に出版した本書は、原題《Sur la télévision》のとおり、テレビという巨大な影響力をもったメディア(マスコミ)への批判となっている。そこで指摘されている問題点は、現代日本においても同様の状況になっているものだろう。そのときだけおもしろければよいという風潮においては、ある話題はネットにおけるバズとして強調され広まるが、あっというまに古びたものとなり、忘れられていく。この一連の流れは当然のものではなく、印象操作されたものである。この問題は根深く、簡単に解消できるものではない。2024/11/06
抹茶ケーキ
1
タイトル通りのメディア批判。メディアは「三面記事」的なゴシップを報道するのに汲々としており、本当に必要な情報を提供していないとのこと。その批判自体はありきたりだけど、ブルデューの中心概念であるハビトゥスや象徴暴力、場などの概念が使われているので、ブルデューの他の本を読んだ後に読むと理解が深まって面白いかもしれない。2018/01/15
ぽん教授(非実在系)
1
三面記事的イエロー・ジャーナリズム的なジャーナリストが大衆迎合的な姿勢により数字による人気取り・商業主義に走る様子はフランスであっても変わらない。その意味では、ブルデューはエリートの再生産の構造を暴露した学者ではあるものの、やはり軽い大衆がじっくり熟議をする知識人を駆逐していくのが嫌いなのであろう。市場主義が大衆の反逆を後押しする存在として描かれているところはユニーク。2015/08/10
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢の追放後! 教会改革ごはんで悠…