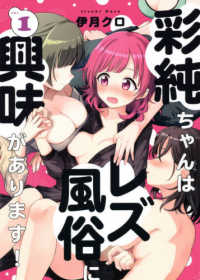内容説明
完結。文芸批評をのりこえる「作品科学」の方法論。闘争を科学する。
目次
第2部 作品科学の基礎(方法の問題;作者の視点―文化生産の場の全般的特性)
第3部 理解することを理解する(純粋美学の歴史的生成;眼の社会的生成;読みの現実態理論)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
9
文学作品をそれ自体の内部の関係として読む内的読解の超越性に対し、作品と社会や歴史等外部との関係として読む外的読解は言語の超越性に依拠するとした著者は、両者の超越性を排した生成の場に文学作品を置き、文化資本の生産の場面から文学作品を捉える。『感情教育』に3つの場と作者フローベールのハビトゥスを読む前巻を受けた本巻で著者は、19世紀産業社会で振興ブルジョワジーの移動の頻度が、眼という器官を中心に美学を再編成し、作品の自律性という文学的信仰が生産されることを示しつつ理解することを理解する「作品科学」を提唱する。2024/05/17
む
1
芸術の価値を決める(=価値への信仰を生産する)のは各々が正統性を獲得するために行う椅子取りゲーム。ある芸術作品の価値は共存する他作品との関係(対立/相同、支配/被支配…)の網目=場の中で決まる。同じことだがこの場には多数の位置があり、作品と作家はどこかの位置に分類され、それをもって闘争する。ただ厄介なのはゲームの規則は作品生産により絶えず変わること。〜主義が混沌とする世紀末(ここでは象徴派とデカダン派、自然主義くらいに言及)を勉強するなら必読。文学とはこうである、なんて言えなくなる(言ってもいいけど)。2022/08/18
SQT
1
ブルデューのこれまでの作品における、あるいは(1)でのフローベールの読解に対する理論的な部分がまとまっている感じ。文学場champは自律的になり、そこにおける知覚評価図式は歴史的に再構築されなければならないものになる。本質的なものがそこにあると見誤るとよくない、みたいな話だと思うけど、なんか読んだときは納得〜という感じ((1)よりもわかりみが深い)だけどレビューが難しい…わかったようなわからんような。ただブルデューのほかの作品と要旨がそこまで違っているようには見えないので読み比べて例と共に理解するのが吉か2017/11/17
鏡裕之
1
<場>の考え方に、緻密さが欠けているように感じる。文学場に読者を入れてしまうと、市場はどうなるんだということになる。対象が文学ということもあるのか、ブルデューの分析もいわゆる文学批評の凡庸さに引きずり込まれている。可能態の空間については定義が適当だが、これはいつものブルデュークオリティ。2015/07/11
-

- 洋書電子書籍
- Three Men in a Boat…