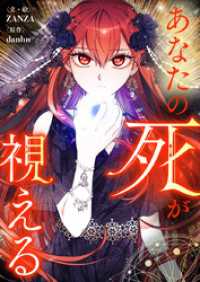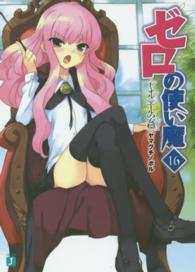内容説明
文芸批評をのりこえる「作品科学」の誕生。「内的読解」と「外的読解」の不毛なアンチノミーを克服し「文学場」の生成と構造を活写。
目次
フローベールの分析者フローベール―『感情教育』のひとつの読み
「場」の三状態(自律性の獲得―「場」の出現の決定的段階;二元的構造の出現;象徴財の市場)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ラウリスタ~
14
再読。こんなすごい本だったか。プロローグで『感情教育』内の文学、芸術場の分析。本文ではその著者フロベールを中心として、彼が二つの否定(ロマン主義にもレアリスムにも)によって自分の立場を獲得することについて。社会学的分析は単に作品を環境の産物に還元するのではなく、作家がいかにしてその環境の決定要因から抜け出し「創造主」となったのか理解することを目指す。そのためにこそ、名もなき郡小作家を学ぶことに意味がある(大作家たちも、彼らへの反発によって自己形成した)。商業的成功と同業者評価は常に交差配列(ヒエラルキー逆2022/11/13
ラウリスタ~
12
フロベール『感情教育』の社会科学的読み方の提示をプロローグにする。文学作品をある時代、地域、社会階層の必然的結果として説明するのではなく、そこからの解放を可能とした作家の芸術的独自性を説明するために、逆説的に、社会科学的読解は有用。「知識人」とはゾラによって発明された地位だが、それは政治的に積極的に参加することによってではなく、その逆に、文学が社会的な規定の数々(道徳的、政治的な)者から独立しているとする「文学の自律性」を打ち立てたことによって、初めて可能になったアンガジュマンなのだ。といった感じの逆説美2018/01/27
roughfractus02
6
文学テクストの自律性から「作者の死」へ転回する文学批評のアプローチに対して、著者は文化資本の生産の一部として、作家固有の習慣形成(ハビトゥス)と文学場(=界の結びつき)の考えによって作家と作品を捉え直そうとした。19世紀後半の産業社会下のフランス文学を対象とした本書は、唯一の創造者としての作家という考えを批判し、誰が作家を創造したのかと問い、その唯一性を力のせめぎ合う場において創造される作家の特異なハビトゥスに置き直す。本巻はフローベール作品を例に学生界・貴族界・芸術界の重なり合う文学場の検証から始まる。2024/05/16
nranjen
6
わからないところは大学図書館で借りてきた原文(文庫!?)で確認しながら、メモ取り、重要なところは抜き取りしながら読んだ。でもまだまだモレがありそう…。そもそもブルデューの文体が論述のプルーストかと思われるほど関係詞で後にずらずらと連なっていくタイプらしく、訳出(正確)も大変だったと思うけれど、そんな訳を読むのも結構面倒な作業なのだ。でもよく読むと小ネタも面白いし、大枠も面白い。概念の構図も面白い。何より今目の前の現実にも応用できる。一冊で何度も美味しい。2019/06/30
nranjen
3
再読。持ち本だと何度も読めるという長所があることを実感。どの単語がどのような言葉で訳されているのかを注意深く見てみる。序は文学と社会学についての著者の姿勢を打ち立てる宣言文でもあることに気づく。 第二巻を読まずに売ってしまったことも(/ _ ; )2019/04/19