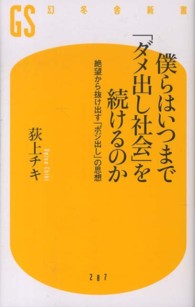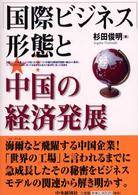内容説明
本書は、インド仏教の衰亡をメインテーマに据えたおそらく世界最初、少なくともわが国においては最初の書物である。ではなぜ仏教はインドの地で衰亡してしまったのであろうか。この問いは、不思議と日本はおろか、世界でも真剣に検討されてこなかった。本書はこの問いに真正面から取り組んだ著者十数年間の苦闘の成果である。
目次
第1章 宗教とは何か
第2章 インド仏教衰亡説の検証
第3章 イスラム史料『チャチュ・ナーマ』とは
第4章 『大唐西域記』と『チャチュ・ナーマ』の対照研究
第5章 西インド社会と仏教
第6章 イスラム教のインド征服と仏教
第7章 最初期のインドのイスラム教
第8章 他地域における仏教の衰亡
第9章 比較文明論からの考察
第10章 社会変革の手段としての改宗
第11章 アメリカの社会と宗教
第12章 結論
著者等紹介
保坂俊司[ホサカシュンジ]
1956年群馬県渋川市出身。早稲田大学大学院文学研究科修了。現在、麗沢大学国際経済学部教授、早稲田大学政治経済学部非常勤講師、財団法人東方研究会・東方学院講師、財団法人モラロジー研究所研究員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
bapaksejahtera
12
イスラム勢力が北西インドを征服した事績を基に書かれた年代記「チャチュ・ナーマ」を基として考察を加えた本。印度文化の基層に染み込んだカースト制度の下では、下層カーストや周辺民族は浮かび上がれない。仏教は当初反/抗バラモン教として成立したが、次第に支配権力の庇護を受け、富裕商人の寄進に依存するうち、信徒組織基盤脆弱なまま、タントラ仏教に変貌する。それ故イスラムによる組織と施設の破壊は致命的で、一般信徒はイスラムに包摂された。本書からかく理解した。印度文化とスーフィズムとの親和性について、更なる論及が欲しかった2024/11/03
kenitirokikuti
10
図書館にて。2004年刊行。仏教はインドで発しながら、なぜその地で途絶えたのか(少なくとも、ジャイナ教は亡んでいない)。日本では研究の薄い分野であり、著者も中村元から君たちが挑むよう言われたとある▲日本では玄奘の『大唐西域記』は有名だが、それとほぼ同時代・同地域を扱った記録『チャチュ・ナーマ』を扱っている。711〜13年にインドの地を初めて征服したムハマド・カーシムの事績である。このカーシムが滅したのがエフタルの末裔が建国したラーイ王朝(王が仏教徒)。2025/07/26
Yuichi Sasaki
2
副題にもあるように、イスラム史料『チュチュ・ナーマ』に基づき、『大唐西域記』などの諸資料のクロスチェックを経ながら、インドにおける仏教滅亡の社会的文明的背景を探る。従来ほとんどなかった比較文明的視点からの分析で、インド社会のみならず中央アジア地域におけるダイナミックな文明の動向を論じる。 ただし、あくまでイスラムや仏教やヒンドゥーの制度的側面からの視点が多く、教理的な側面からの分析は少ない。イスラム史料からの臆断を交えながら述べる箇所には、いささか性急さも感じる。ミクロな視点からの研究が期待される。2012/08/20
大道寺
2
インド仏教の衰亡を、仏教教団ではなく仏教社会(文明)の衰亡と捉え、比較文明の方法論を用い、8世紀前半に書かれたとされるイスラム史料『チャチュ・ナーマ』を基礎にして、考察する。インドへのイスラムの伝播は711年という。『チャチュ・ナーマ』はイスラム教のインドへの初伝の経緯をイスラム側で記録した書物である。(1/3)2012/06/30
非実在の構想
1
教理ではなく社会構造に着目し、仏教からイスラムへの改宗の過程を追っている。腑に落ちる主張が多かった。しかし、このクソコラのような装丁は何なのか。 2017/09/15