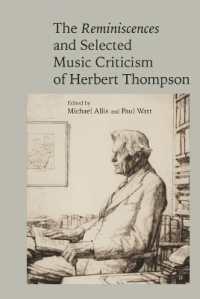- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
内容説明
「もう誰にも会いたくない」と思ったことはありませんか?ここで語るのは、もうひとりのあなたです。「ひきこもり」経験者15人へのインタビュー。
目次
勝山実―僕の中にまだいるんですかね「プチエリート」くんが
岩田紀美子―仲間は他にもいっぱいいることを知って欲しい
松下秀明―どうして入院させたんだと父を問いつめた
宮坂由貴―たぶんすごく必要な時間だと思う、それがわかるのは出てきてから
望月道代―まわりの人から見るともどかしくて「何やってんねん」と思うかもしれへんけど
小林貴彦―人と同じペースではやっていけない、ちょっとずつ前進していけばいいと思っています
沢田祐一―やっぱり妻子に救われている部分は大きいと思いますね
新井宏之―その声を聞いてすごく俺のことを考えてくれているんだと感じたんです
水口康介―いくら何でも甘えだと思ったらそう言ってもいいと思う
井上香織里―ひとりでもがいていても生きるエネルギーが消費されるだけだと思った〔ほか〕
著者等紹介
田辺裕[タナベユタカ]
1971年東京都生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。フリーライター
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コーキ
0
理想と現実の乖離。悪、矛盾、不条理に耐えられない素直さ。親、先生、友達の影響。重圧、押し付け、すれ違い。インターネット、本、ゲームへの逃避。色々と共通項はあるんだろうけど、それでもやっぱり一般化してはいけない。一般化は人を救わない。「分からなさに耐えること」。それが大事。2014/11/24
鈴と空
0
2006年以前
kirico
0
ひきこもり当事者さんたちへのインタビュー。共感できなくて途中で挫折しそうになりましたが、最後まで読むことができました。 読んでみれば、絶望感はそれほどではなくて、なんだか希望の光もほのかに見えるような… その理由は、あとがきの田辺さん(取材、文)と斎藤環医師のまとめの文が大きいかなと思います。 当事者でないわたしたちに出来ることは、共感できるかどうかを議論するよりも、社会問題化しているひきこもり問題への対策を邪魔しないことじゃないでしょうか。社会の損失には違いないのですから。2022/08/17
May
0
引きこもり経験のある人達が、その半生を語る本。 性格は、内向的な人もいれば、活発だった人もいて様々だった。 しかし、家庭環境は親からの勉強しろという圧力を受けていたり、学級委員や生徒会に入ったり、引きこもる前は優秀だった人が多い印象を受けた。 それと、少し考えすぎてしまう人も多いかもしれない。 概して押しつけは逆効果になると思った。2019/04/28
ちひろ
0
意外だったのは問題なく小学校や中学校、高校くらいまで過ごしていてもちょっとしたつまづきでひきこもるケースも少なくないんだなということ。子ども時代にレジリエンスをつけさせたいと親である身としては考える。そして結局どんなに人が苦手だったり嫌いだったりでも、多くの人は人と関わる中で安心感や幸せを感じていくのかなということ。これは2000年発行の古い本なので、ネットが当たり前になった現代の本も読みたい。2019/01/16