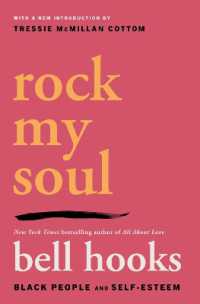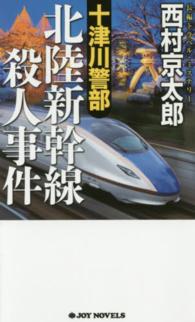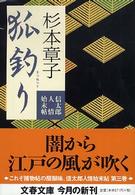内容説明
シュタイナー教育の全学年・全教科をシュタイナーの助言でたどる。
目次
緒言―幼年期・学童期・思春期
国語(ドイツ語)
算数・数学
理科
物理
化学
生活科
地理
歴史
外国語
美術
音楽
芸術史
体育・オイリュトミー
手芸・手仕事
工芸
技術
概観
著者等紹介
シュタイナー,ルドルフ[シュタイナー,ルドルフ][Steiner,Rudolf]
1861‐1925年。ウィーン工科大学に学び、21歳でドイツ国民文学双書の『ゲーテ自然科学論文集』の編集を担当。1891年、フィヒテの知識学を扱った論文で哲学博士号を取得したのち、ベルリンで文芸・演劇評論誌を編集。20世紀に入ると同時に、ロシアの神秘思想家H・ブラヴァツキーの創始した神智学運動に加わり、1912年、アントロポゾフィー(人智学)協会を設立。独自の精神科学に基づいて、教育、医学、農業、建築、社会論などの分野に業績を残した
西川隆範[ニシカワリュウハン]
1953年、京都市生まれ。スイスとドイツでシュタイナー精神科学を研究。シュタイナー幼稚園教員養成所(スイス)およびシュタイナー・カレッジ(アメリカ)客員講師を経て、多摩美術大学講師、自主学校〈遊〉オープンハイスクール講師、学校法人シュタイナー学園評議員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
も
1
各教科、随分細かく教える内容や時期が決まっているんだな。点数で評価しないとはいえ「この歳でこれは教えなきゃ」という意図は強く感じる。「フワフワした、子供の好き勝手にさせる教育(勉強したくなきゃしなくていいよ的な)」ではないことは確かそう。 教師が教科書を読まない、自らの知で語る、というのは自分が通った私立高校と似てるなと思った。私は小中は特に面白かった出来事の記憶が無い。2024/04/23
モート
1
15歳の頃に、ドイツに行って受けたいと思っていたシュタイナー教育。当時、日本の教育と常識は、国の成長とともにフェーズチェンジできず、過去の成功例に囚われた相変わらずの主知主義と上意下達型の金太郎飴教育だった。大人の今でも、シュタイナー教育のテイストを主体的に日常で行えることがたくさんある。だから行うし同時にコーチできる。2018/06/08
もちゆき
0
国語、算数など教科ごとに学年別での学ぶポイントを分かりやすくまとめてある。7歳頃からの学びかたの解説がメインだったので自分には早すぎた、子どもが成長したら再読しようとおもう。2016/04/01
aray
0
主客二分じゃない教育。アストラル体など独善主義と取られかねないため、現代では非科学的と切り捨てられそう。だが、多様性とポストトゥルースの時代において、プラグマティズムの復権が来ると思っている。つまり、学習が体験から切り離されない学びにおいては、私がどう体験するかがまさに学習だからである。2024/08/08