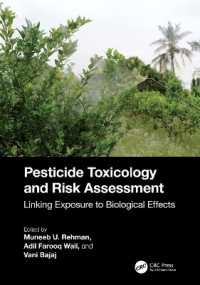内容説明
本書は日本人がよって立つ足元の稲作漁撈文明の価値の再発見を行い、その稲作漁撈文明によって新たな文明世界を構築することを提案するものである。
目次
日本人よ、欧米文明の幻想から自立せよ(歴史観の大転換が必要;自然の見方の転換も必要 ほか)
第1部 泥の文明のパワー(泥の文明(稲作漁撈文明)と石の文明(畑作牧畜文明)
砂の文明(遊牧文明))
第2部 稲作漁撈文明と人類の未来(聖樹の崇拝;殺し合いを回避する社会 ほか)
第3部 文化の多様性と生物の多様性を破壊する市場原理の超克(市場原理は過去のもの;文明は衝突しない ほか)
著者等紹介
安田喜憲[ヤスダヨシノリ]
国際日本文化研究センター教授、環境考古学者。1946年三重県生まれ。1972年東北大学大学院理学研究科修士課程修了。1974年東北大学大学院理学研究科博士課程退学。広島大学総合科学部助手をへて、理学博士。1988年国際日本文化研究センター助教授。1994年同センター教授。1995年麗澤大学比較文明文化研究センター客員教授。1996年中日文化賞受賞。フンボルト大学客員教授。1997年~1999年京都大学大学院理学研究科教授(併任)。1991~1994年文部科学省重点領域研究「文明と環境」事務局、計算研究代表者。1997年~2001年文部科学省COE拠点形成プロジェクト「長江文明の探求」などのビッグプロジェクトのリーダーをつとめる。2001年11月地球科学や生態学などのノーベル賞に匹敵するクロホード賞の候補に日本人としてはじめてノミネートされ、ノーベル財団の招致でスウェーデン王立科学アカデミーで講演。2006年4月スウェーデン王立科学アカデミー会員
松本健一[マツモトケンイチ]
麗澤大学国際経済学部教授、評論家。1946年群馬県生まれ。1968年東京大学経済学部卒業。1974年法政大学大学院日本文学研博士課程。1983年北京日本語研修センター(外務省)教授。1989年~京都精華大学教授。1994年~麗澤大学教授。1997年~日韓合同学術会議座長。法政大学大学院で近代日本文学を専攻。在学中に『若き北一輝』を発表し話題となる。95年『近代アジア精神史の試み』でアジア・太平洋賞、2002年「日本の近代1開国・維新」で吉田茂賞。2005年、第8回司馬遼太郎賞。また、『評伝 北一輝』(全5巻)により第59回毎日出版文化賞
欠端實[カケハタミノル]
麗澤大学教授、中国古代史、比較民俗研究。1939年東京生まれ。1963年早稲田大学第一文学部卒業。1965年早稲田大学大学院文学研究科史学専攻卒業。1971年より財団法人モラロジー研究所勤務。1977年より麗澤大学勤務
服部英二[ハットリエイジ]
麗澤大学比較文明文化研究センター客員教授、モラロジー研究所道徳科学研究センター教授・研究主幹。1934年生まれ。京都大学大学院博士課程修了。1961年ソルボンヌ大学博士課程留学。帰国後、日本ユネスコ協会連盟事務局長などを務め、1973年より、ユネスコ・パリ本部勤務。主席広報官、文化担当特別事業部長などを歴任。その間に「科学と文化の対話」シンポジウム・シリーズ、「シルクロード・対話の道総合調査」等を発足させる。1995年フランス共和国より「学術・教育功労賞」オフィシェ位を授与される。その後、麗澤大学教授を経て現在、道徳科学研究センター研究主幹、ユネスコ事務局長官房特別参与、国際比較文明学会副会長、日仏教育学会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
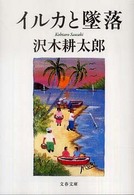
- 和書
- イルカと墜落 文春文庫