内容説明
少女文化、音楽、青少年マンガ、性的メディアをその内容・歴史・データなどあらゆる面から分析し、システム理論によって戦後の若者のコミュニケーションに新たな光をあてる画期的なプロジェクト。
目次
第1章 少女メディアのコミュニケーション
第2章 音楽コミュニケーションの現在
第3章 青少年マンガのコミュニケーション
第4章 性的コミュニケーションの現在
第5章 サブカルチャー神話解体論の地平
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メルキド出版
10
社会学読書会で「序説」扱うため読む。メディアに表れたコミュニケーションとしての少女マンガ、音楽、宗教の分析をする。それらは学習(モデル)段階、実践(ツール)段階、反省段階の組合せの構造がある。本書のテーゼはサブカルチャー分析は「好きなもの」「浮遊」「退却」「学術」で留まると批判し、みずからの啓蒙を促す。ちなみに私見でTwitter言説の観察すると、本書指摘の「終末論的・黙示録的」な覚悟系と「仏教的・自我論的」な修養系の対立がみえる気がする。さしずめ自分は「陥没した眼差し」の浮遊系だろうか……2024/07/06
pochi
1
1998年 3月11日
aquirax_k
1
アーカイブに自由にアクセス(違法だけど)出来るようになった今、この理論は通用しがたいと思うけど。まぁ面白い。
-
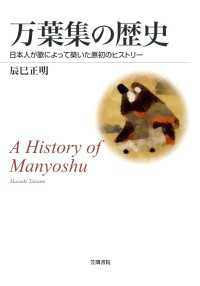
- 電子書籍
- 万葉集の歴史 日本人が歌によって築いた…
-
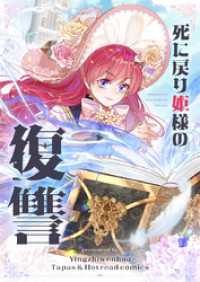
- 電子書籍
- 死に戻り姫様の復讐【タテヨミ】第59話…







