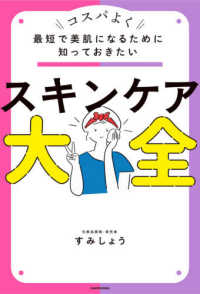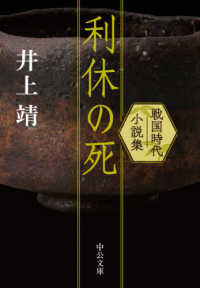内容説明
究極的には、主題さえ持たない芸術作品。それが“作者”の望みだ。まったく物語のない小説。“死の類別目録”小説。
著者等紹介
マークソン,デイヴィッド[マークソン,デイヴィッド] [Markson,David]
1927年、アメリカのニューヨーク州オールバニーに生まれ、2010年、グリニッチヴィレッジに没した。小説家、詩人
木原善彦[キハラヨシヒコ]
1967年、鳥取県に生まれる。京都大学大学院文学研究科英語学英米文学専攻博士課程修了。現在、大阪大学大学院言語文化研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田氏
19
〈読者〉は感想を書くのを本気でやめたがっている。 ダニエレブスキーは小説の脚注にもう一つの小説を書いた。 柳瀬尚紀は脚注を使わずにジョイスを訳した。 これは感想だ。〈読者〉かラウシェンバーグがそう言えばそうなのだ。 サルバドール・プラセンシアは人物の心情描写を黒く塗りつぶした。 ジョナサン・サフラン・フォアは本を切り刻んで詩を紡いだ。 あるいは、言葉による表現の極地への憧憬だ、もしも〈読者〉がそう言えば。 『嫌ならやめとけ』。 あるいは、安易で稚拙な模倣だ、もしも〈読者〉がそう自認すれば。2019/09/10
aoneko
15
殆ど知らない事実ばかりだった為、読み応えがあって、なかなか面白かった。<作者>の語りに少し複雑な気持ちになったり、時に、まぁ作家というのは酷いことを言うものだなとヘンに感心させられたり。ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』をブルーム教授が1時間33分で読了する、ってスペクタクルには笑った。語られる順番が絶妙。 2014/01/28
きゅー
14
最後まで読み終えても、たしかに物語はなかった。何らかの仕掛けにより、主人公が浮かび上がるということもない。しかしなぜだろう物語性を持った一級の小説のように面白く、「物語」に引き込まれるようにしてページを繰る自分がいた。古代ギリシアから現代アメリカまで、芸術と名のつく分野の人々が登場して、よくこんなことまで調べたなと思わされる圧倒的な情報量。それに加えて、文章間の緩い連帯の妙が効いている。それにしてもこの一冊のエッセンスを吸い取ろうと思うと大変な知識が必要になる。実験的で、非物語的だけど、愉しい一冊。2013/12/26
メセニ
13
タイトルに興味をそそられつつ「すかしてんとちゃう?」とやや斜に構えたが、訳者が木原氏だからと手に取り長らく積んでいた。およそ主題と言えそうなものはなく、筋立てはおろか登場人物も無し。あるのは短い文や言葉の羅列。それも古今東西の偉人にまつわる雑学を〈作者〉が思うままにツイートしているような態。実はそこにある一定のリズムや構造に気付くが、すると面白いほど読ませる(膨大な註は無視!)。脳汁が出るほどでないし結局はよく分からん本だけど、この闇雲な読み応は何か。ナンセンスなグルーヴに身を任すのも悪くない?非推薦!?2017/12/05
m_s_t_y
11
何でしょうこの小説は。「<作者>は文章を書くのを本気でやめたがっている。」という一文から始まるように「普通」の小説ではない。誰かの死因や、言葉、引用などの断章がひたすら続き、ところどころに著者自身の言葉。こう書くとまともに読めそうにないのに不思議とページが進む。そしていつの間にか読みながら断章にツッコんで笑っている自分に気づく。断章の並びが絶妙なんだと思う。自分にもっと教養があったらもっと面白かったと思うけど、註と人名註がとても充実しているので大丈夫。変な小説好きの人におすすめ。2013/10/01