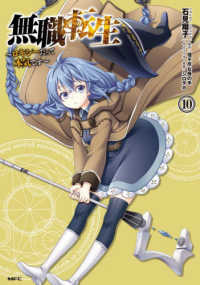内容説明
強欲なクロッシュ婆さんや、道楽で人をただ観察しつづける謎の男ルグラン、脅しで人に寄生して生きる小人ベベ・トゥトゥ、住民の手紙を盗み読むことを趣味としているアパート管理人サチュルナン、日々倦みながらフライドポテト屋でウェイトレスをするエルネスティーヌ。さまざまな人物の思惑、生が交錯する陰謀譚。ミステリーあり、言語遊戯あり、数学的な仕掛けありの、あらゆるクノーらしさのつまった怪物作。銀行員マルセルは、たまたま立ち寄った場末のフライドポテト屋で、ガラクタ屋の老人と出会う。物を持たない幸せを語るその貧しい老人の家には、彼が決して手放そうとしない謎の青い扉があり、町ではそれを巡り、ある噂が囁かれはじめる…。バタイユやデスノスが、ただこの作品を讃えるためだけに、ドゥマゴ賞を創設することとなった、クノーの処女作にして代表作。
著者等紹介
クノー,レーモン[クノー,レーモン][Queneau,Raymond]
『はまむぎ』でドゥマゴ賞を受賞
久保昭博[クボアキヒロ]
1973年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。パリ第三大学博士課程修了(文学博士)。現在、京都大学人文科学研究所助教。専攻、フランス文学、文学理論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
三柴ゆよし
26
<ゴム製のアヒルから始まる、田舎町での陰謀譚>と帯にはあるが、実際には特筆すべき陰謀など存在せず、一風変わった人物たちが、本来であれば取るに足らない事象の背後に(各々が勝手に)陰謀の種を見出していく物語、とひとまずは言えるかもしれない。そうして見出された(生み出された)陰謀は、他の人物の脳内において新たな陰謀の萌芽となり、奇妙な陰謀説は増殖を反復する。そもそもこのおかしな小説は、ひとつの影として登場した人物が三次元的な質感を得た瞬間を、ひとりの観測者が発見するシーンをもって幕開けとするのだが、(続)2012/07/19
長谷川透
23
この小説の書き出しはいかにも上品な純文学という感じだったので身構えてしまった。けれども、言葉遊びの連続、ブラック・ユーモアそして「陰謀譚」と銘打っておきながら、滑稽とも言える物語展開は、いかにも『文体練習』の著者らしい。ところが物語を読み進めることは決して平易ではなく、ふと油断すると振り落とされてしまう危険さえある。次第に、天蓋からこの小説を読む自分をレーモン・クノーが眺め、ニヤニヤと笑っているような気配を感じるようにもなった。解説を読み、著者の企みには度肝抜かれた。著者の底知れぬ知性には怖畏を覚える。2012/07/25
pyoko45
15
何とも不思議な面白さ。物語の筋はけっこう複雑で、色々と細かい伏線を拾ってゆく楽しみに溢れています(「おお、あれとあれはつながっているのか!」的な発見がいろいろと)。ただ、大きな話の流れは、軽やかに無邪気に跳躍を織り交ぜて突き進み、要約困難。人を喰ったような言葉遊びや、小道具/小ネタのバカっぽさが、ホームドラマ的なほのぼの感を醸していて笑えます。出だしのモヤモヤ状態に尻込みしましたが、最後まで読んで唸りました。なるほど、そういうことか。2012/07/02
兎乃
13
久保訳、面白いです。装丁はコレクションの基調を揃えるという意味もあるのかもしれないけど、渦巻きグルグルのほうが良かったかもしれない。発表当時は文壇から黙殺されたクノーの処女作。憤慨したバタイユやレリス、ロジェ・ヴィトラックをはじめとする13人の友人達が、パリの老舗カフェ「ドゥ・マゴ」において即座に一人100フランずつポケットマネーを出し合って賞金1300フランをクノーに授与。これがドゥ・マゴ賞となったわけです。7章×13節、1~13までの自然数総和 且つ第一回ドゥ・マゴ賞受賞作品、お読みあれ。面白いデス2012/07/23
Mark.jr
5
Raymond Queneauの作品の中で一番筋の抽出が難しく、訳の分からない小説なわけですが。改めて読むと、登場人物全員がこれが小説であることを理解して下手な演技をしている感じが、後のヌーヴォーロマンに繋がる一作であることがよく分かります。何冊か翻訳出てますが、この全集バージョンが一番読み安いかと。2026/01/03