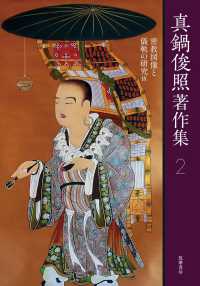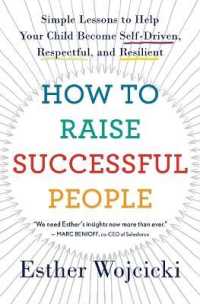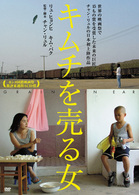内容説明
スピノザという異形の運命に立ち戻り、その批判的/転覆的意味、および彼によって先取りされた“共”の哲学を、現代思想に布置するための最もラディカルなガイダンス。訳者によるアクチュアルな解説を付す。
目次
序章 スピノザとわたしたち
第1章 スピノザ―内在性と民主制の異端
第2章 力能と存在論―ハイデッガーかスピノザか
第3章 スピノザ政治思想の展開におけるマルチチュードと個別性
第4章 スピノザ―情動の社会学
著者等紹介
ネグリ,アントニオ[ネグリ,アントニオ][Negri,Antonio]
1933年、イタリア・パドヴァ生まれ。思想家、活動家、哲学者、アウトノミアを代表する理論家、指導者
信友建志[ノブトモケンジ]
1973年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、龍谷大学、京都大学非常勤講師。専攻、思想史・精神分析(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
大ふへん者
6
『野生のアノマリー』は大著なのでまずはこれから。かなり読むのに難儀しそうだと予感していたが、信友氏の訳が易しく読みやすい。(先日読了したステファヌ・ナドー『アンチ・オイディプスの使用マニュアル』も氏による訳で読みやすかった)ネグリによるスピノザ解釈が充分に理解できたかと言われれば怪しいが、他著で頻繁に登場する「マルチチュード」「〈共〉」等の概念素地は掴めたか。取り分けスピノザの「内在性」「コナトゥス」「力能」が如何に政治的現在性をもつかという点が整理できてよかった。未読の『神学・政治論』も読まなきゃ。2014/02/01
amanon
4
まずタイトルが良い。単なる思考の遊戯ではない哲学とは何か?という著者の思いが反映されているように思う。理解の程は怪しいが、今日においてスピノザをいかに読み、理解するか?そしてそれをいかに実社会に反映させるか?ということが主たるテーマではないか?ということは朧げながら理解できた気がする。また、何より大きいのは、改めてスピノザを読み返してみようという気にさせられること。『エチカ』のような透徹したスタイルと文体がこれまで数多くの人々を熱狂させたという不思議。その熱狂の一端が本書にも伺える。また読み返したい。2017/11/09
1.3manen
2
2006年度慶應通信哲学特殊でスピノザを学んだ記憶がある。本著はハートとの共著『帝国』で有名なネグリによるもの。講演録だが内容が難しい。重要タームはゴシック太字とはいえ、概念の理解が困難である。イタリア語からの邦訳となっている。訳者解説を参照すると、スピノザの基礎概念は「力能」(potential)である(184ページ)。他にもマルチチュード、コナトゥスも頻出している。存在として面白いのは、コグニタリアート(認知労働者)の存在である(197ページ)。情動労働という労働が新産業や新しい社会のカギかもしれぬ。2012/10/28
シベリア研修所
1
ネグリのスピノザに関する講演等をまとめた比較的新しい論集。序章はやや難解だが、後の章は、スピノザに関してある程度読んだことがあれば読みやすい。ネグリがスピノザについてどのように考えているか手頃に知りたい方にはそこそこいい本だと思う(『野生のアノマリー』は分厚い上に難解だし、Subversive Spinozaはそもそも翻訳が無い)。翻訳も悪くは無い。2012/01/05
里のフクロウ
0
「哲学する」とはいかにすることかを探し求めているところにふと手にした。スピノザが世を賑やかしてという。手にしてから難解と言われていることを知った。初学者には無謀な挑戦となった。それでもなんとか読破、いくつかのキーワードを取り出すことは出来た。マルチチゥード・コナトゥス・力能・欲望・愛・情動。スピノザは近代に身を委ねることはなく、ポスト近代へと飛び越して、資本経済社会後の社会に「情動」を見出している、というふうに私は勝手に納得して終えた。折角難解な文体を読み通せたのでスピノザをもう一冊挑戦することにした。2015/03/10