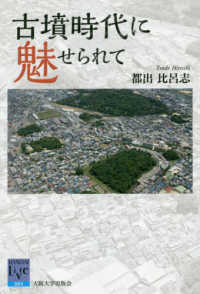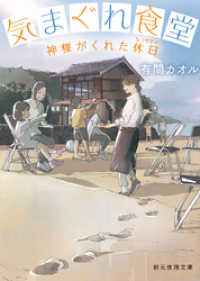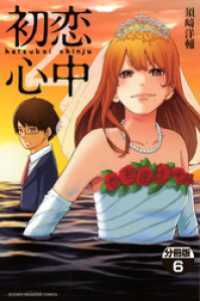内容説明
民衆の統合支配はどのようにして実現するのか?ナチス、大本教、イタリアにおける実践など、しばしばその類縁性を指摘される“宗教”と“ファシズム”の関係を、歴史的・文化的諸相によって捉え返し、いま‐この時代の経験へと逆照射する画期的な論集。
目次
はじめに ファシズム期の宗教と文化
第1部 「遅れてきた国民」の宗教と政治(救世主幻想のゆくえ―皇道大本とファシズム運動;超国家主義と日蓮主義―カルトとしての血盟団 ほか)
第2部 文明のなかの非合理的なもの(イギリスの宗教研究とファシズム;初期レヴィナスのファシズム論―“自由のユダヤ=キリスト教的なライトモチーフ”について ほか)
第3部 宗教研究はファシズムをどう経験したか(宗教学からネオナチ出版界へ―「ヨーロッパ宗教史」を語る「宗教学」と「極右」;ファシズム期のイタリア宗教史学―民族学、フォークロアの流れのなかで)
第4部 両大戦間期の神話研究(植民地帝国日本の神話学―昭和前期の日本神話研究を中心に;なぜ私は印欧語族研究を止めたか)
著者等紹介
竹沢尚一郎[タケザワショウイチロウ]
1951年、福井県に生まれる。フランス社会科学高等研究院博士課程修了、博士(民族学)。現在は国立民族学博物館教授。専攻、社会人類学、アフリカ史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mittsko
2
本書の特徴は、ファシズムと《宗教》というよりも、ファシズムと《宗教学、およびその関連諸学》の関係を分厚くあつかった点 後者はつまり、「学」として制度化されていたけれど、広い意味での「文化運動」、とりわけ「宗教的な心性ないし宗教的なものへの希求」(編者)の当時における現れであった(それはまた、本書では展開されていないが、近代的な宗教概念の成立過程そのものでもあった)ということ 決定的に重要な論点だが、多くの読者には馴染み薄なんだろうなぁ… 一度目次をご覧になってほしい一冊です2011/08/24