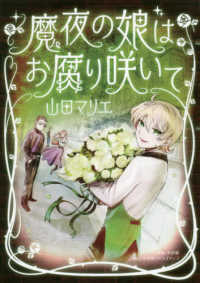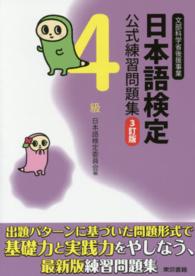内容説明
ポップ心理学、資本主義、そして死。混沌が支配する日常を“くたばらず”に生き抜くために、ガタリ=ドゥルーズはいかに実践しうるのか?カフカ、プルースト、三島由紀夫、『スター・ウォーズ』、バッグス・バニーを駆使する、鮮烈なエクリチュール機械の誕生。
目次
第1部 まずエディプスに受かってからにしなさい(ニコラ;ポップ心理学から出てくるのはこんなもの;「おまえのほうがエディプスだよ!」;アンチ・オイディプス)
第2部 測量(主体性と隷従;死と生;メランコリーとノスタルジー;時(間))
結論ではないけれど
補遺1 選択の意志
補遺2 ポップ哲学
著者等紹介
ナドー,ステファヌ[ナドー,ステファヌ][Nadaud,St´ephane]
1969年生まれ。フランス現代思想研究、児童精神科医
信友建志[ノブトモケンジ]
1973年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。思想史・精神分析専攻。現在、龍谷大学および京都大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Bevel
2
自分の興味と真正面にかみ合うものではなかったが、こういう『アンチ・オイディプス』の読み方もあるのか、と思った。ポップ心理学の部分は、定式化がはっきりしていて面白かった。以下で、ナドーの見ているコード化と領土化について考えてみる。2012/11/03
1
再読。語り口が逆にうざいw三島由紀夫の「生と死の哲学」が如何にして資本主義のノスタルジーに回収されていったことに対しての批判、プルースト論から資本主義の時間からの「失われた時」(=差異)を対置するところが面白い。問題は、資本主義のシステムが脱領土化するのではなく、個体を主体化することへの指摘か(「ポップ心理学」への批判もここに起因)「自殺」の問題をフーコーの思想とも繋木しながら論じているがとにかく翻訳の問題なのか、崩した口調なのにめちゃくちゃ読みにくい。2024/01/28
大ふへん者
1
10日ほどかけてじっくり反芻しながら読了。『アンチ・オイディプス』の正しい読み方、ではなくまさに『アンチ・オイディプスの使用マニュアル』である。ポップ心理学(個体を道徳的価値への再領土化に閉じ込める)と資本主義(個体の強いられた主体化システム)と民主主義(平和=生の称揚)の共犯関係といかにして戦うかヒントをもらった。システムへの隷従に取り込まれることなく個体を主体化する(脱隷従)ことは幻想であり、集合的な主体が作られることに委ねるほうがましだろうと著者は考える。私もかなり近い考えを模索中だ。2014/01/10
じょに
0
pp.76-792010/04/14
Yuki
0
『アンチ・オイディプス』における資本主義機械の「公理化」論を仮想敵とし、「現在」と「過去」の自我を非時系列(超-時間)的に捉えることで、両者のあいだに生じる差異こそを資本主義機械と闘う「武器」と称する。/上記の非時系列な自我(主体性)を導出する理論は、精神分析的な観点(ノスタルジーとメランコリー)からなされ、当該部分単体において、アルチュセールやバトラー、フーコーらの主体化理論と比較する試みにも関心が湧いた。2025/04/07
-

- 電子書籍
- 姉ヶ崎さんは幸せになりたい 3巻 A-…
-

- 和書
- 地方財閥の展開と銀行