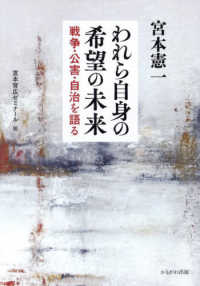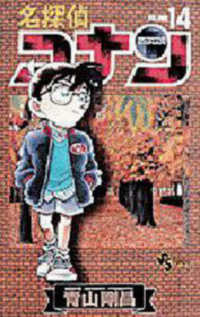目次
序論 ジョルジュ・バタイユと造形芸術の問題をめぐる地図
第1章 割れた鏡の中から、亀裂を抉りながら―『ドキュマン』における写真使用法
第2章 『ドキュマン』における不定形の美学―イデアリスムに抵抗する唯物論
第3章 芸術の誕生をめぐって―『ラスコーあるいは芸術の誕生』、芸術の生成的価値と内在性
第4章 人間の形象―『ラスコーあるいは芸術の誕生』『マネ』『エロスの涙』を結ぶ線
第5章 表象の抹殺、口を開く裂け目―『マネ』と現代絵画の誕生
結論 形態の下にあるもの
著者等紹介
江沢健一郎[エザワケンイチロウ]
1967年、埼玉県川口市に生まれる。明治学院大学文学部フランス文学科卒業、立教大学大学院文学研究科フランス文学専攻博士課程後期課程満期退学。博士(文学)。専攻、フランス文学。立教大学、法政大学、日本社会事業大学兼任講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
0
再読。バタイユの芸術論、つまり「不定形」(=アンフォルム)の思想を検討する。まず、『ドキュマン』の写真の衝突のモンタージュからピカソのブルトンの「超」(=合一)の解釈からその枠組みに必然的に漏れ出てしまう内在的な「低次唯物論」的な解釈を対置させる。この「低次唯物論」=「異質学」の論理的な担保をギリシア以前、つまりラスコーの壁画に見出す。バタイユは一貫して、人間の認識の枠組みを漏れ出てしまう未分化の「ある」=「非-知」のざわめきが噴出する「傷口」を見出そうとする。それは、「マネ論」で極限に達する。2024/02/21
-

- 電子書籍
- サイレント・ウィッチ【ノベル分冊版】 …
-
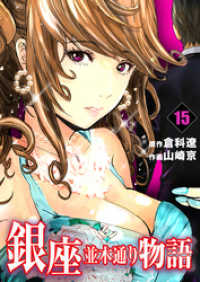
- 電子書籍
- 銀座並木通り物語 15 レジェンドコミ…