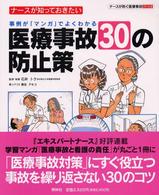出版社内容情報
本書「大地の砂金」は、「砂金堀り物語」(脇 とよ著)と「平成の砂金堀り」(北代祐二著)の2部で構成されている。
砂金堀りにロマンをかき立てられる者にとって、永遠のバイブルともいえる幻の名書、「砂金堀り物語」が50年ぶりに、復刻版として今、蘇える。
明治、大正、昭和にかけて<北海道の砂金堀り師>として名高かった渡辺良作が、妖しく光る山吹色の金の砂の魅力に取り憑かれ、生涯を砂金堀りに賭けた。
後半の「平成の砂金堀り」では平成の砂金掘り師で知られる北代氏が、砂金掘りの楽しみ方を親切に解説している。
砂金堀りに関心のある方々にとっては、待望の一冊だ。
「砂金堀り物語」
・なぜ砂金掘りになったか
・雨宮敬次郎北海道砂金採取団員となる
・採取道具とその使い方
・砂金堀りのあしあと
この物語は、北海道で約50年間、砂金掘りとして一生を終えた山形県三泉村出身の渡辺良作が、明治19年27年ごろまであったという雨宮敬次郎氏の砂金探険団の団員として体験した当時のできごとをおもにし、砂金掘りになるまでの彼の少年時代のことを綴ったものです。
土地名、人名、採取用具、採取法、北海道アイヌのこと、食用植物のことなどもすべて、良作が63才のころに語ってくれたそのままであります。したがって、あるいはまちがいがあるかもしれません。(中略)良作の少年時代が、わりに長くて、北海道のことがシリキレトンボのようになってしまいました。けれど、それは良作の少年時代を、良作自身が、非常に深く、忘れがたくおもっていたため、しばしば語ったことをみんな書きたかったからです。
良作はこののち、北海道に一家をあげて移住しました。良作と父親は、後志、胆振、十勝はもちろん、天塩、石狩、北見、と北海道全地にわたって、ありとあらゆる砂金鉱区をまわって砂金採取をしました。その間には良作の父親が、大熊の襲撃にあい、山中で死ぬという悲惨なこともあり、また良作が父の仇をさがしまわってついに大熊と格闘してそれを斃すなどの勇ましいこともありました。んか、地獄や極楽はこの世のなかにあるもんだ、おらが死んでもだれにも知らせるでない、骨は高野山にすててくれ」といい言いしたものでした。遺言どおりに高野山のお寺の炎のなかに、良作の小さい骨壷は、またたく間に灰となってしまったのです。
そして良作老人が残して死んだものは、かの、絹の上下の着物と、羽織と、へこ帯と、そして、かわいい砂金のサオバカリとよごれた地図でありました。そうそう、それだけではありません。良作おじいさんは、この物語を残して逝ったのでございます。
1956・10 脇 とよ 「砂金掘り物語」 あとがき より
昭和31年11月20日初版発行
前半の「砂金掘り物語」は、著者の脇 とよさんが、物語の主人公である生前の渡辺良作から直に聞いた話をもとに、昭和31年出版されました。関係者の間では、読みたくても入手が難しく、幻の名書と云われてきました。砂金に関心がない人でも、主人公良作の砂金に憑かれた数々の行状には、魅力を感じずにはいられません。また、これから砂金堀りを楽しみたい方には、後半の「平成の砂金堀り」(北代祐二著)のなかで、北代氏が初心者のために親切に解説されております。是非ともお読みいただきたい1冊です。