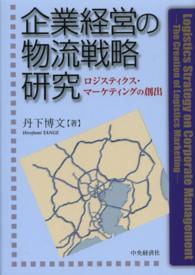内容説明
一九一四年六月のサラエボ事件に端を発した第一次世界大戦は、三〇カ国以上が参戦し、ヨーロッパを主戦場に四年三カ月も続く史上初の総力戦だった。戦車、機関銃、飛行機、毒ガス、潜水艦などの近代兵器が初めて戦場で本格的に使われ、延べ六五〇〇万人の将兵が動員された。兵士たちは凍てつく大地や泥濘の塹壕で戦い、八六〇万人の戦死者を出し、民間人の犠牲者はさらにそれを上回った。戦争はいかに始まり、どのように戦われ、ヨーロッパに何をもたらしたのか?開戦経緯から各国の戦争計画、主要会戦の実相、終戦まで、多くの戦争指導者に焦点をあてながら明らかにする。長年研究を続けてきた著者が膨大な資料をもとに知られざる第一次大戦の全容に迫る。
目次
サラエボ事件
直前外交
シュリーフェン計画とマルヌ会戦
タンネンベルク殱滅戦
ガリシアの戦い
ロッヅ付近の戦闘
第一次イープルの戦闘
ゴルリッツ突破戦
ロシア軍の秋季反攻
第二次イープルの戦闘
ベルダン攻防戦
ブルシロフ攻勢
ソンムの戦い
ニベルの攻勢
ロシア革命
第三次イープルの戦闘
カイザー戦
連合軍の最終攻勢
著者等紹介
別宮暖朗[ベツミヤダンロウ]
1948年生まれ。東京大学経済学部卒業。西洋経済史専攻。その後信託銀行に入社、マクロ経済などの調査・企画を担当。退社後ロンドンにある証券企画調査会社のパートナー。歴史評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
K
16
タイトル通り陸戦に焦点を当て、1914年8月から1918年11月までのWW1の戦闘に関する通史を紹介(ただし東部戦線と西部戦線がメイン。中東等の副次戦線の記述無し)。WW2や現代の国際情勢との関連を示すメタ的な文章は、自分としては鬱陶しく思えたが、専門書ではなく一般書としては許容範囲。参考文献の洋書は極めて古いものばかりであり、最新の欧米の歴史学研究の成果とは異なる記述もあるが、日本語でWW1の主要戦闘を学ぶには大きな影響はないより専門的な内容へ進むための導入として本書を活用すればよい。2024/11/15
ELW
0
参考文献にジョルを挙げていないのは遺憾。そのまんまの表現もあるくらいなのに。開戦に至った経緯は、ジョルよりはだいぶん分かりやすい。しかし、高校世界史の教科書でこれを三国同盟対三国協商、帝国主義で教えてし まっているのは辛いし、正確に教えるのは更に辛いか。ドイツ軍の捕虜がどのようにでるのかとフランスの抗命事件の中身がよく分かった。『8月の砲声』を読んでおいて良かった。2015/07/06
小澤 泰裕
0
この戰爭は、すでにクラウゼヴィッツが考へたやうな政治の延長ではなくなつてゐる。2014/07/05