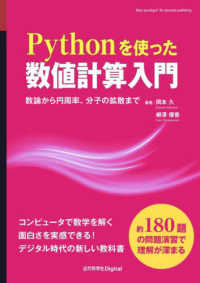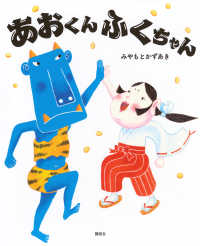出版社内容情報
《内容》 本邦に於ける消化管内視鏡検査は,従来胃を中心としたものであった. しかし近年大腸疾患の症例の増加は著しく,大腸内視鏡検査に十分熟達していなければこの領域の専門家として通用出来なくなってきた. 大腸内視鏡は,現在ファイバースコープと電子スコープが共存するものの,電子スコープがファイバースコープにはない高度の機能を有し,しかも同時に複数の医師での検査が可能な所から急速に電子スコープが優位に立ちつつある. 大腸内視鏡検査は胃のそれと違って,各人の力量の違いが大きい.またそれぞれの疾患が症例毎にかなり異なる複雑な様相を示し,内視鏡診断を難しくしているのも周知の所である. この様な背景から,大腸内視鏡検査の手技に重点を置いた書物,炎症性疾患,あるいは早期大腸癌のみに対象をしぼった書物はこれまでにも多数上梓されてきている. しかし一冊の書物で内視鏡の機器から検査手技さらに諸疾患の内視鏡診断,鑑別診断まで要領よく網羅した書物はないといっても過言ではない. 本書出版の意図はまさしく一冊の書物で,この全領域を要領よくカバーすることにある. 幸い多数の執筆者のご賛同を戴き,この様な編集方針で本書を上梓することが出来た. まず冒頭の数章では基本となる機器の理論,構造,その取り扱い,検査手技を説明した.特に検査手技は,複数の方に異なる立場から,手技のこつともいうべき事項を詳述して戴いた.前処置についても各種の方法を記述し,施設の実情に応じて選択出来る様試みた. ついで正常大腸の所見を説明し,主要な疾患については,その所見の読みと共に関連した事項を細かく取り上げ,日常の診療に十分役立つことを心掛けた.さらにそれぞれの疾患で今日問題になっていることにも触れ,今後の研究,将来の動向に向けて突っ込んだ記載を試みた. 加えて色素法,拡大観察,超音波内視鏡検査などにも触れ,内視鏡的治療も必要最低限ではあるが解説した. 検査にあたっては照診による診断のみならず,所見の再検討の為の写真撮影あるいは磁気的な記録,的確な生検の実施,さらに内視鏡治療の為にも詳細な観察が前提になることはいうまでもない. しかも内視鏡検査に際しては,動きのある対象を短時間に正確に把握し判断を進めなくてはならない.このため本書では,的確に検査を行う上に必要な事項を漏れ無く取り上げる様に努めてみた. 以上により本書は大腸内視鏡検査をこれから始める方のみならず,高度の専門家にとっても十分役立つ内容になったものと自負している. 座右に備えて戴き,日常の診療の場で必要に応じ紐解いて戴ければ編者ならびに執筆者にとって望外の幸と思っている. 《目次》 第1章 内視鏡機器とその取り扱い 1.電子スコープ 黒沢 進,中村孝司 I.電子スコープの原理 II.大腸電子スコープの取り扱いと各操作部の仕様 1.操作部の機能 1)アングルの機能 2)吸引ボタン,送気,送水ボタンおよびリモートコントロール用スイッチ 3)鉗子孔 2.スコープ挿入部 3.先端部 III.電子スコープの使用法の実際 IV.保管上の注意 2.ファイバースコープ 黒沢 進,中村孝司 I.大腸ファイバースコープの取り扱い II.操作部における接眼部と装着カメラ III.操作部(図) IV.先端部 第2章 検査に必要な解剖学 三嶋秀行,西庄 勇,吉川宣輝 I.大腸 1.肛門管 2.直腸 3.S状結腸 4.下行結腸 5.横行結腸 6.上行結腸 7.盲腸 II.大腸壁の構造 III.大腸の血管支配 IV.大腸のリンパ系 第3章 適応と禁忌 光藤章二,斎藤彰一,外嶋 敬 I.適応 1.目的 2.診断 1)炎症性腸疾患 2)腫瘍性病変 3)その他の病変 3.治療 1)腫瘍切除 2)上血術 3)減圧術 4)拡張術 5)異物除去術 6)S状結腸軸捻症の整服 7)抗癌剤の局注 8)術前のマーキング II.禁忌 1.絶対的禁忌 1)急性腹膜炎 2)腸管穿孔 3)心肺疾患の急性期 4)腹部大動脈瘤 2.相対的禁忌 1)高度な炎症性腸疾患 2)腸閉塞 3)妊娠 4)高度な腹水 5)高度な腸管癒着 6)前処置が不良な場合 7)意識障害のある患者 8)大量出血中の患者 第4章 機器の洗浄・消毒 小越和栄,斉藤征史 I.内視鏡機器の洗浄・消毒の必要性 II.内視鏡による患者間感染の実態と感染経路 III.内視鏡機器(大腸鏡)の洗浄・消毒の実際 1.大腸内視鏡の洗浄 2.内視鏡機器の消毒 1)内視鏡機器消毒の手順 2)消毒剤の選択 3.処置具の洗浄・消毒 IV.環境の消毒 第5章 結腸検査のための前処置 1.マグコロール法 岩井淳浩 I.大腸検査前処置の原則 II.各前処置法の特徴 III.非等張マグコロール法(従来法)の実際と問題点 IV.大量等張マグコロール法の実際 V.大量等張マグコロール法の利点 VI.大量等張マグコロール法の欠点 2.その他の前処置法 田中信治,春間 賢 I.大腸内視鏡検査の前処置 1.前処置法の種類 a)Golytely法 b)在宅Golytely法 c)大量マゴコロールP法 d)検査食併用Golytely法 e)経腸栄養剤を用いた前処置法 f)下剤 g)消化管機能調律薬 2.前処置における注意事項 a)検査前日の食事内容についての注意 b)腸管付着粘液,気泡に対する対策 c)合併疾患 II.患者への説明と対応 1.患者への説明 2.患者への対応 III.前投薬 1.鎮静剤 2.鎮痙剤 3.前処置と腸管内ガス 岩井淳浩 I.腸管内爆発の機序 1.爆発の要因 2.腸管内ガス 3.腸内細菌による発酵 4.燃焼に要する最少酸素量 5.発火温度 II.各種前処置における腸管内爆発性ガス濃度 1.マンニトールによる前処置 2.Polyethylene glycol electrolyte lavage solutions (PEG-ELS)による前処置 3.現在わが国で多く用いられている前処置間の比較 III.患者背景因子による影響 1.食物繊維の影響 2.豆類の影響 3.他の食事の影響 第6章 電子スコープによる検査 1.一人法と二人法の選択 岩井淳浩 I.一人法と二人法の現況 II.一人法の独走の理由 III.教育に適した二人法 IV.一人法と二人法の選択 1.一人法 2.二人法 3.内視鏡下処置の時 V.今後の一人法と二人法 2.一人法での基本操作 a.硬いスコープの操作法 田村 智 I.大腸の走行 II.前投薬 1.鎮痙剤 2.鎮静剤 3.鎮痛剤 III.大腸内視鏡挿入 1.術者のレベルの問題 2.術者の姿勢と被験者の体位 3.部位別挿入法 1)直腸への挿入 2)RsからS状結腸へ 3)S状結腸から下行結腸へ 4.脾彎曲部の越え方 5.横行結腸の進め方 6.肝彎曲部の越え方 7.盲腸から回腸末端部へ b.軟らかいスコープの操作 光島 徹 I.大腸内視鏡開始前の注意事項 II.スコープ挿入手技 1.肛門から直腸・S状結腸部へ 2.直腸・S状結腸部からS状結腸へ 3.肛門側S状結腸からS状結腸・下行結腸移行部へ 3.S状結腸・下行結腸曲の越え方 4.肛門則下行結腸から脾弯曲部へ 5.脾彎曲部の越え方 6.横行結腸脾彎曲から肝彎曲部へ 7.肝彎曲部の越え方 8.上行結腸肝彎曲から盲腸へ 9.回盲弁の越え方 3.二人法での基本操作 小山 洋,笹木淳司 1.二人法の種類 1)逆「の」の字型挿入法 2)当院における二人法 II.当院における二人法の実際 1.概要 2.二人法の利点 1)両手によるアングル操作(とくに左右アングル) 2)習得が容易 3)疲労が少ない 4)安定した姿勢 III.挿入技法 1.腸管ひだの基本的な越え方 2.スコープの直線化 1)1カーブ越えたら引き戻し法 2)2カーブ越えたら引き戻し法 3)S状結腸のループ解除 3.体位変換 4.用手圧迫法 5.吊り天秤法 6.深呼吸 IV.各部位におけるトラブル対処法 1.直腸・S状結腸移行部(Rs)を越えられない場合 1)ゆっくりとした挿入操作 2)体位変換してみる 2.S状結腸の途中(肛門縁から30cm前後)で痛みを訴える場合 1)腹壁を用手圧迫する 2)鎮静剤,鎮圧剤を使用する 3.S状結腸の途中(肛門縁から50 cm) で痛みを訴える場合 1)被検者に深呼吸させる 2)体位変換する 3)左トルクをかけて,用手圧迫する 4)用手圧迫する 4.S状結腸でスコープがとぐろを巻いて痛みを訴える場合 5.S状結腸・下行結腸移行部(SDJ)を越えられない場合 1)もう一度,スコープを直線化する 2)体位変換する 3)用手圧迫する 6.SDJを越えたのにスコープが前に進まない場合 1)トルクをかけながら挿入する 2)用手圧迫する 3)S状結腸途中の屈曲をSDJと誤認している 7.脾彎曲部を越えたのにスコープが前に進まない場合 8.横行結腸の右半分にスコープが進入できない場合 1)体位変換する 2)用手圧迫する 9.肝彎曲部を越えられない場合 1)ゆっくりとした操作 2)空気の吸引 3)体位変換する 10.肝彎曲部を越えたのにスコープが前に進まない場合 1)用手圧迫する 2)深呼吸させる 4.硬度変換式スコープでの操作 a.太いスコープでの操作 佐竹儀治 I.硬度可変式スコープの仕組み II.硬度可変式スコープによる挿入法 1.S状結腸の通過 2.横行結腸から深部への挿入 3.挿入時のその他の注意 b.細いスコープでの操作 多田正大 I.硬度可変式スコープ開発の歴史的背景 II.硬度可変式スコープの開発目的 III.硬度可変式大腸鏡・CF-240Aによる挿入法 IV.挿入成績 5.検査のコツと留意点 a.挿入困難部位での操作 五十嵐正広 I.挿入手技 1.基本操作 2.肛門から直腸へ 3.直腸の通過 4.Rectosigmoid(RS)からS状結腸へ 4.S状結腸,S状・下行結腸移行部(SD)の通過 1)αループでの挿入 2)逆αループでの挿入 3)Nループの挿入 6.脾彎曲の越え方 7.横行結腸から上行結腸へ 8.上行結腸から盲腸,終末回腸へ b.補助器具の応用 町田マキヨ,佐竹儀治 c.X線透視下コントロール 多田正大,沖 映希 d.挿入形状観測装置の開発 多田正大,草場元樹 6.撮影と記録 川口 淳,宮崎純一,永尾重昭 I.電子スコープの利点 II.撮影と記録の問題 III.撮影と記録と重要性 IV.撮影記録における留意点 V.フィルムを後で見直すことの重要性 VI.撮影記録の将来 第8章 出血時の緊急内視鏡検査 五十嵐正広,小林清典,勝又伴栄 I.出血例に対する禁忌と適応 II.緊急検査の前準備 1.内視鏡下局所洗浄法 2.出血部位の確認 III.緊急検査の実際と診断 IV.内視鏡的止血法 第9章 色素法の応用 1.色素散布法 今村哲理 I.コントラスト法 II.染色法 2.経口法 岩井淳浩 I.大腸経口色素法の特徴 II.使用する色素の条件 III.用いられる前処置法の条件 IV.色素の投与量・投与時間 V.実際の方法 VI.検査時の注意事項 VII.適応と禁忌 VIII.成績 IX.実際の内視鏡像 第10章 拡大鏡の応用 加藤茂治,藤井隆広,田尻久雄 I.拡大内視鏡の機能と挿入法について 1.挿入法(CF200Zによる) 1)Rs-S移行部 2)S-D junction 3)脾彎曲部 4)横行結腸,肝彎曲部 2.新型の拡大内視鏡(CF-Q240Z)について II.腺口形態(pit patttern)分類と組織診断 III.拡大観察の適応病変について IV.拡大観察の手技について V.症例提示 第11章 超音波内視鏡検査 趙 栄済,中島正継 I.超音波内視鏡検査(EUS)の意義 II.使用器械 III.正常層構造 IV.癌 V.Sm癌 VI.粘膜下・壁外病変 VII.潰瘍性大腸炎 VIII.EUSの現状と展望 第12章 生検と基本的治療手技 1.生 検 北野厚生,鈴木典子,大庭宏子,足立賢治,中村志郎,押谷伸英,松本誉之 I.生検の基本的手技 I.スコープ操作 2.的確な視野の確保 3.生検操作の困難な病変 II.各種疾患に対する生検上の注意点 1.腫瘍性疾患 2.炎症性腸疾患 1)潰瘍性大腸炎(UC) 2)クローン病(CD) 3)腸結核 4)腸アメーバー症 2.基本的治療手技 上堂文也,飯石浩康,竜田正晴 I.内視鏡切除法の手技と注意点 1.ポリぺクトミー 2.粘膜切除術 3.大きな病変を安全に摘除するための工夫 1)有茎性腫瘍 2)広基性腫瘍 II.内視鏡的止血術 第13章 偶発症の発症と症状,予防について 1.概 論 金子榮藏 I.偶発症の内容と変遷 1.本邦のおける全国調査および海外の報告に見る偶発症の頻度 2.偶発症の内容 2.穿孔と出血時の症状 丹羽寛文 I.偶発症の種類と頻度 II.穿孔について 1.穿孔部位 2.穿孔に気づいた所見 3.穿孔確認までの時間 4.穿孔の原因 5.X線透視のコントロールとスライディング チューブ 6.穿孔と術者の経験度 7.治療と予後 III.出血について 1.部位ならびに年齢 2.出血に気づいた所見 3.出血確認までの時間 4.出血の原因 5.X線透視とスライディングチューブ 6.術者の経験度 7.治療と予後 IV.結腸紐の断裂と漿膜の裂傷 V.偶発症防止のために 3.予 防 大川清孝,青木哲哉,追矢秀人 I.挿入に伴うもの II.内視鏡治療に伴うもの 1.穿孔 1)ポリペクトミー 2)粘膜切除 3)ホットバイオプシー 2.出血 1)被検者の術前評価 2)ポリペクトミー 3)粘膜切除 第14章 検者に対する注意 勝 健一 I.検査前インフォームド・コンセント II.検者の感染症に関する安全対策 III.内視鏡検査室の安全対策 2.法律的注意点 a.医師法,保険医療担当規則 b.薬事法 c.刑法 第15章 大腸の正常所見 酒井義浩 I.挿入時の直腸 II.挿入時のS状結腸 III.導入時の下行結腸 IV.挿入時の横行結腸 V.挿入時の上行結腸・盲腸 VI.盲腸の観察 VII.回盲弁の観察 VIII.終末回腸の観察 IX.送気による伸展時の粘膜像 X.抜去時の右結腸曲 XI.抜去時の左結腸曲 XII.他臓器の陰影,拍動 XIII.抜去時の直腸 第16章 炎症所見の性状と鑑別診断 1.病変の分布,色調,潰瘍随伴の有無 宇野良治,棟方昭博 I.通常内視鏡による炎症の観察法 II.病変の分布,色調,潰瘍随伴の有無 1.潰瘍性大腸炎 2.Crohn病 3.虚血性腸炎 4.回盲部から横行結腸の炎症 5.直腸の炎症 6.全大腸に及ぶ炎症 2.潰瘍所見と鑑別 a.潰瘍の分布 宇野良治,棟方昭博 b.円形潰瘍 宇野良治,棟方昭博 c.不整形潰瘍 宇野良治,棟方昭博 d.縦走潰瘍 宇野良治,棟方昭博 e.輪状潰瘍(circular ulceration) 宇野良治,棟方昭博 f.瘢 痕 宇野良治,棟方昭博 g.潰瘍周辺粘膜の性状 宇野良治,棟方昭博 3.アフタ様病変 芦澤 宏,三浦総一郎 I.概念 II.病因 III.病態 1.臨床所見 2.臨床検査成績 3.注腸検査所見 4.内視鏡所見 5.病理組織学的所見 6.診断と鑑別診断 1)クローン病 2)潰瘍性大腸炎 3)ベーチェット病 4)赤痢アメーバ性大腸炎 5)腸結核 6)他の感染症腸炎 7)大腸リンパ濾胞増殖症 8)薬剤性腸炎 9)“アフタ様大腸炎”(吉川ら) 4.炎症性ポリポーシス 三浦総一郎,芦澤 宏 I.内視鏡所見 1.潰瘍性大腸炎 2.クローン病 3.腸結核 4.赤痢アメーバ 5.直腸粘膜脱症候群 6.日本住血吸虫 第17章 潰瘍性大腸炎 1.疾患概念,診断基準 牧山和也,竹島史直 I.概念 1.概念の変遷 2.概念 II.診断基準 III.内視鏡診断手順 2.内視鏡所見 牧山和也,竹島史直 I.内視鏡的最小単位病変 II.典型的内視鏡像 III.活動期病勢による内視鏡分類 1.軽度 2.中等度 3.強度 IV.経過中にみられる多彩な内視鏡像 1.炎症所見の非定型的分布を呈するUC 2.緩解期萎縮性粘膜像 3.炎症性ポリポーシスを伴った萎縮性粘膜の再燃時像 4.“skip lesion”としてのいわゆるulcerative appendicitis像 5.回腸末端部病変 V.内視鏡的生検の意義 1.生検の目的と方法 2.組織学的特徴 1)活動期 2)回復期から緩解期 VI.色素内視鏡検査の意義 3.鑑別診断 牧山和也,竹島史直 I.アメーバ性大腸炎 II.偽膜性大腸炎 III.放射線照射性大腸炎 IV.直腸粘膜脱症候群(mucosal prolapse syndrome of the rectum) V.クローン病 VI.アフタ様大腸炎 VII.虚血性大腸炎 4.潰瘍性大腸炎と皮膚病変 丹羽寛文 I.結節性紅斑(erythema nodosum) II.壊疽性膿皮症(pyoderma ganagrenosum) III.血疱 IV.口内炎 V.肛門・肛門周辺病変 5.長期経過での粘膜変化 丹羽寛文 症例1 症例2 症例3 症例4 6.Displasiaと癌化,フォローの基本方針 川口 淳,穂苅量太,永尾重昭 I.潰瘍性大腸炎の癌化にはどのような危険があるのか II.どのような点に注意すべきか―癌化の特徴に関して 1.年齢 2.罹病期間 3.性 4.発生部位の特徴 5.組織型の特徴 6.肉眼型の特徴 7.罹患範囲と病型の特徴 8.病変における遺伝子診断 III.どのようにフォローすべきか 第18章 クローン病 1.疾患概念,診断基準 朝倉 均 I.疾患概念,診断基準 II.診断基準 1.縦走潰瘍 2.敷石像 3.非乾酪性類上皮細胞肉芽腫 4.アフタ様びらん・不整形潰瘍 5.全層性炎症性病変 III.診断 1.問診 2.他覚所見 3.一般検査 4.造影X線検査 5.内視鏡検査 2.内視鏡所見 本間 照,朝倉 均 I.縦走潰瘍 II.敷石像 III.縦列する不整形潰瘍またはアフタ IV.上部消化管病変 3.外瘻と肛門病変 本間 照,朝倉 均 I.発生頻度 II.肛門病変 1.Skin lesions 2.Fissures 3.Anal stenosis/stricture 4.Abscess 5.Fistula III.痔瘻と腸管病変との経時的関係 4.鑑別診断 朝倉 均 I.症状からみて鑑別すべき疾患 1.急性虫垂炎 2.大腸憩室炎穿孔 3.膠原病 4.鉄欠乏性貧血 II.急性下痢疾患 1.急性回腸末端炎 2.虚血性大腸炎 III.慢性下痢疾患 1.潰瘍性大腸炎 2.腸結核 3.Behcet病,単純性腸潰瘍 4.アメーバ赤痢 5.非特異性多発性慢性小腸潰瘍症 第19章 急性感染症 1.検査上の注意 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 I.前処置 II.内視鏡室の対応 III.検者,介助者の保護 IV.検査材料採取上の注意点 V.内視鏡機器の洗浄,消毒 VI.処置具の滅菌 2.赤 痢 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 3.病原性大腸菌O-157腸炎,その他 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 4.サルモネラ 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 5.キャンピロバクター 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 6.腸炎ビブリオ 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 7.エルシニア腸炎 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 第20章 その他の慢性感染症 1.腸結核 馬場忠雄,宇田勝弘 2.アメーバ赤痢 永尾重昭,松崎宏治,川口 淳 3.サイトメガロウイルス腸炎 江川直人,加藤裕昭,榊 信廣 4.日本住血吸虫症 滝川崇弘,斉藤 豊,藤井隆広 第21章 虚血性大腸炎 北野厚生,押谷伸英,中村志郎,松本誉之,大川清孝 I.疾患の概念と病態 II.内視鏡像(直視画像) III.治療方針 IV.治療の実際 第22章 抗生物質起因性腸炎 1.急性出血性腸炎 大川清孝,青木哲哉,追矢秀人 I.抗生物質起因性腸炎の概念 II.急性出血性腸炎の概念 III.臨床像 IV.内視鏡像 V.鑑別診断 VI.診断の手順 2.偽膜性腸炎 大川清孝,青木哲哉,追矢秀人 I.概 念 II.臨床像 III.内視鏡像 IV.鑑別診断 V.診断手順 第23章 1)分類 板橋正幸 I.炎症性ポリープおよびポリポーシス II.良性リンパ濾胞性ポリープおよびポリポーシス(benign lymphoid polyp and polyposis) III.過形成結節・過形成性ポリープ IV.過誤腫性ポリープおよびポリポーシス(hamartomatous polyp and polyposis) 1.Peutz-Jeghers症候群 2.若年性ポリープおよびポリポーシス(juvenile polyposis) 3.Cronlhite-Canada症候群 4.Cowden病 V.腫瘍性ポリープ 1.腺腫 2.腺癌 3.特殊な腺腫および癌合併病変 1)結節集簇様病変(lateral spreading tumor,creepring tumor) 2)過形成型混合腺腫(mixed hyperplastic adenomatous polyp;MHAP),鋸歯状腺腫(serrated adenoma) 4.大腸ポリポーシス(とくに腺腫症) VI.カルチノイド腫瘍 2.形態別,組織別の内視鏡像の典型所見 渡辺聡明,武藤徹一郎 I.形態別分類 1.有茎性ポリープ 2.広基性ポリープ 3.表面隆起型病変 4.結節集簇様病変 II.組織型別分類 1.腫瘍性ポリープ 1)腺管腺腫(tubular adenoma) 2)絨毛腺腫(villous adenoma) 3)腺管絨毛腺腫(tubulo-villous adenoma) 4)villous tumor 2.非腫瘍性ポリープ 1)過誤腫性ポリープ a.若年性ポリープ b.Peutz-Jeghers型ポリープ 2)炎症性ポリープ 3)良性リンパ濾胞性ポリープ 4)化生性ポリープ(metaplastic polyp) 3.治療の適応 工藤進英,田村知之 I.最新の内視鏡診断に基づくポリープの取り扱い 1.一般的事項 2.Over polypectomyの終焉―pit pattern診断がもたらした新しい考え方 3.生検の問題点と必要性 4.Sm癌の取り扱い 5.注意すべき病変―陥凹型由来と考えられるIs型(Is+IIc) 4.フォローについて 佐野 寧,大桑正名,藤井隆広,加藤茂治 I.Total colonoscopyにおける見逃しの可能性からみた検査間隔の設定 1.各群における腫瘍発生率と検査間隔 2.切除病変の個数・組織型と腫瘍発生率 3.検査回数と腫瘍発生率 II.5mm以下の表面型大腸腫瘍の経過観察 1.腫瘍径および肉眼径の変化 III.今後のfollow-up colonoscopy 第24章 ポリポーシス 1.家族性大腸腺腫性ポリポーシス 丹羽寛文 2. 3. 4.Cronkhite Canade syndrome 永尾重昭,中島弘幸,川口 淳 第25章 粘膜下腫瘍 渡辺聡明,武藤徹一郎 1.平滑筋腫 2.脂肪腫 3.血管腫 4.リンパ腫 5.良性リンパ腫 6.その他 第26章 悪性腫瘍 河原正樹,上西紀夫 1.進行癌 I.進行癌の定義・形態分類 II.進行大腸癌診断における大腸内視鏡の意義と問題点 III.確定診断のための内視鏡所見 1.癌の診断 2.深達度診断 3.広がり診断 IV.進行大腸癌の内視鏡像 1.1型(腫瘤型) 2.2型(潰瘍限局型) 3.3型(潰瘍浸潤型) 4.4型(びまん浸潤型) V.部位別の特徴 VI.多発大腸癌 VII.転移性大腸癌 VIII.鑑別診断 1.肉腫・悪性リンパ腫 2.大腸子宮内膜症 3.炎症性疾患 IX.生検の問題点 X.大腸癌の組織発生と内視鏡 2.早期癌 a.隆起型 b.陥凹型,表面型 c.結節集簇性病変,LST d.生検上の問題点,ポリペクトミーの意義,病変に応じた取り扱い 工藤進英,中里 勝 3.肉腫,悪性リンパ腫 小林正明,朝倉 均 I.悪性リンパ腫 II.平滑筋肉腫 III.悪性黒色腫 4.カルチノイド 笹木淳司,小山 洋 第27章 血管性病変,angiodysplasia 浜本哲郎 I.大腸 angiodysplasia 1.概念 2.原因 3.好発年齢 4.症状 5.好発部位 6.診断 7.診断鑑別 8.治療 II.大腸静脈瘤 1.概念 2.原因 3.症状 4.好発部位 5.診断 6.鑑別診断 7.治療 III.Portal hypertensive colopathy 第28章 結腸憩室症 山崎一樹,上西紀夫 I.大腸憩室の発生機序と疫学的事項 II.内視鏡挿入時の注意点 III.憩室症の内視鏡所見 IV.憩室症の合併症の内視鏡 1.憩室出血 2.憩室炎 第29章 その他の疾患 1.放射線直腸炎 久山 泰 2.非特異性大腸潰瘍 久山 泰 3.子宮内膜症 永尾重昭,宮崎純一,川口 淳 4.腸管気腫性嚢胞症 永尾重昭,田中宏史,川口 淳 5.Buerger病 久山 泰 6.単純性潰瘍 久山 泰 7.Behcet病 久山 泰 8.膠原病の腸管病変 久山 泰 9.アミロイドーシス 宮岡正明,木幡義彰,斉藤利彦 10.メラノーシス 宮岡正明,木幡義彰,斉藤利彦 11.腸重積 宮岡正明,木幡義彰,斉藤利彦 12.S状結腸軸捻転症 宮岡正明,木幡義彰,斉藤利彦 13.好酸球性腸炎 宮岡正明,木幡義彰,斉藤利彦 第30章 手術後の大腸,人工肛門からの検査 丹羽寛文 I.経肛門的検査 1.端端吻合 2.吻合部の病変 3.側々吻合,blind loopの形成 4.残存直腸,J-pouchの検査 II.人工肛門からの検査 第31章 直腸の腫瘍性病変 1.粘膜脱症候群 清水誠治 2.宿便性潰瘍 清水誠治 3.急性出血性直腸潰瘍と急性直腸粘膜病変 清水誠治 第32章 肛門部の疾患 碓井芳樹,岩垂純一 I.大腸内視鏡からみた肛門の解剖 II.肛門(肛門管)の疾患 1.内痔核 2.血栓性痔核 3.裂肛 4.肛門ポリープ 5.直腸粘膜脱(直腸粘膜脱症候群MPSの 隆起型) 6.肛門管絨毛腺腫 7.肛門管早期癌 8.肛門管類基底細胞癌 9.肛門管メラノーマ 10.複雑痔瘻(骨盤直腸窩痔瘻) 第33章 虫垂関連病変 櫻井幸弘 I.虫垂切除後の変化 II.急性虫垂炎の内視鏡所見 III.慢性虫垂炎の内視鏡所見 IV.粘液膿腫(Mucocele),嚢胞腺癌(Cystadenocarcinoma) V.虫垂癌 VI.虫垂カルチノイド VII.大腸炎の波及 VIII.瘢痕性変化 IX.寄生虫 X.回盲弁の変化 XI.手術後の変化1 0 1 1999/10/13 0:00:00
内容説明
本書は、大腸内視鏡検査について、まず基本となる機器の理論、構造、その取り扱い、検査手技を説明した。とくに検査手技は、複数の方に異なる立場から、手技のコツともいうべき事項を詳述して戴いた。前処置についても各種の方法を記述し、それぞれの施設の実情に応じて選択できるよう試みてみた。ついで正常大腸の所見を説明し、主要な疾患については、その所見の読みとともに関連した事項を細かく取り上げ、日常の診療に十分役立つことを心掛けた。さらにそれぞれの疾患で今日問題になっていることにも触れ、今後の研究、将来の動向に向けて突っ込んだ記載を試みた。加えて色素内視鏡検査、拡大観察、超音波内視鏡検査などにも触れ、内視鏡的治療も必要最低限ではあるが解説した。
目次
内視鏡機器とその取り扱い
検査に必要な解剖学
適応と禁忌
機器の洗浄・消毒
検査のための前処置
電子スコープによる検査
ファイバースコープによる検査
出血時の緊急内視鏡検査
色素法の応用
拡大内視鏡の応用〔ほか〕