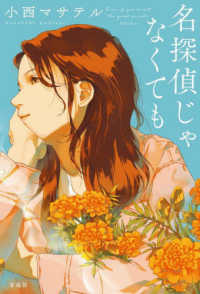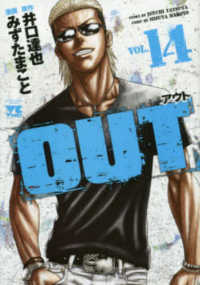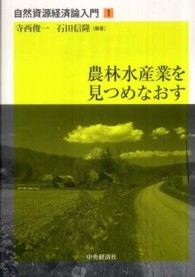内容説明
革新のためには、まずハカれ。トップコンサルタントが教える、一次情報から本質を見抜く技術。BCG、アクセンチュアで磨いた実戦のワザ・公開。
目次
序章 今、なぜ「ハカる」力が必要か?(革新を生むには「ハカる」力が必要だ;ケーススタディで見る、革新を支えた「ハカる」力)
1章 「ハカる」の基本を学ぶ(「ハカる」を定義する;二つの「ハカる」―トップダウン型とボトムアップ型;「ハカる」の基本動作―グラフ・図表にする)
2章 演習で学ぶ!「ハカる」の基本プロセス(FF対ドラクエで学ぶ「ボトムアップ型ハカる」;渋滞問題で学ぶ「トップダウン型ハカる」;三つの挑戦領域で「ハカる」)
3章 第1の挑戦!ヒトをハカる(なぜ、ヒトを「ハカる」のか?;顧客生活をハカってアイデア・ネタ探しをする;顧客評価をハカって商品コンセプトを作る ほか)
4章 第2の挑戦!作ってハカる(実際に作るからこそハカれること;完成品でハカる;試作品でハカる ほか)
5章 第3の挑戦!ハカり方を創る(新しいハカり方への挑戦;テクノロジーでハカる;ヒトでハカる ほか)
補章 「ハカる」の根源(「ハカる」力の根源とは?;数字や行動に落とす;ダイジなモノを選ぶ ほか)
著者等紹介
三谷宏治[ミタニコウジ]
K.I.T.虎ノ門大学院教授。早稲田大学ビジネススクール客員教授。グロービス経営大学院客員教授。1964年大阪生まれ。2歳半から福井で育つ。東京大学理学部物理学科卒業。INSEAD(フォンテーヌブロー校)MBA修了。87年より96年まで、ボストンコンサルティンググループ勤務。96年より06年までアクセンチュア勤務。うち、03年より06年まで同社・戦略グループを統括。同社退職後の07年には区立小学校でPTA会長を勤める。社会人教育の他、大学・高校・中学・小学校での子ども向け・保護者向け・教員向け教育を中心に活動。永平寺ふるさと大使、NPO法人教育改革2020理事、放課後NPOアフタースクール理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Roy。
太田青磁
復活!! あくびちゃん!
唐辛子仮面
msugimo