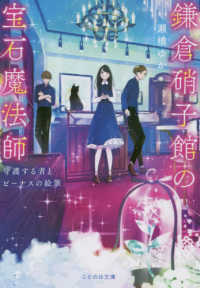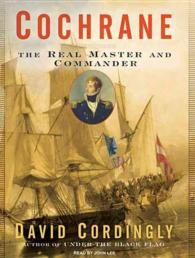目次
第1部 名古屋の電車道(名古屋の玄関・名古屋駅前―名古屋駅前~笹島町;名古屋のメーンストリート・広小路通―笹島町~栄;名古屋の中心・栄 ほか)
第2部 名古屋の電車たち(低床単車;改造単車;1200型 ほか)
第3部 資料編(乗車券・記念乗車券;車両諸元表;配置表で見る車庫所属車両の変遷 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
えすてい
8
廃止路線の多くは市バスで現存してるところも少なくない名古屋市電。保存車両が少なく当初から老朽化で結局解体されてしまったものも少なくないが、科学館やレトロ電車館に残ってる電車の末永い保存を期待したい。名古屋の広い道路も、市電があった時代は「狭かった」のも少なくないのが分かる。当時は車の邪魔ということで廃止へと雪崩打ったが、道幅が広くなった今日(片側5車線の道路とか)、もし市電が残されていたら多分道路環境としては恵まれていたのだと思われる。車両も無音電車の高性能を活かした走行が可能だったと思うが。2020/03/12
えすてい
6
表紙の左側の1421、今もレトロでんしゃ館に保存展示されている。現役当時の写真が見られるのはいい。若宮大通/江川線/空港線/外堀通りは名古屋高速がまだできる前・名駅も伏見も栄も高層ビルがまだない時代。広々とした道路から見えるのは今とは全然違う風景。市電の有無にかかわらず、この当時の光景も今では見られない。2020/03/24
えすてい
6
大正時代の老朽化した木造ボギー車を半鋼製化した1050型と1150型。前者は「カミナリ電車」の高床車のままワンマン改造されずラッシュ時のみの運用となり廃車になったが、後者は低床化改造され一部ドラムブレーキ台車をつけた「セミ無音電車」にしたりワンマン改造されたものもあり、少数は市電最後の日まで残存した。この2型式の命運を分けたものは何だったのだろう。やはり1050型は全長が短く定員が少なかったためか?1150型の方が全長が長く定員も1400型等並みである。「カミナリ電車」ってどれほどの騒音だったのだろうか?2020/03/19
えすてい
2
懐かしい本が今も書店の鉄道書コーナーに並んでいる。重版を重ねてきているので2010年代の今となっては平成のデータや写真であってもすでに過去のものとなっているものもいくつかある。 名古屋市電の車両はあまり鉄道趣味的な話題に上がることはないが、戦前は路面電車初の連接車や汎太平洋平和博覧会に向けての「東洋一の路面電車」・戦後は「無音電車」に代表される全国屈指の高レベルな車両を保有していたのは特筆に値する。残念ながら豊橋鉄道・岡山電軌以外に譲渡されることがなかったので全国的にも馴染みが薄いのだろう。2016/08/08