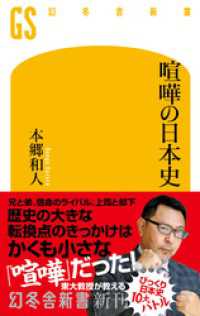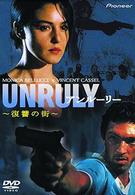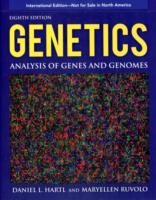内容説明
自ら思考し発見する喜びこそ「学び」だ。断片的な知識の羅列と能率的に「正解する」技術の伝授―こうした授業の反覆は教育を殺す。容易に答えの出ないリアルな課題に取り組み、自ら思考し発見し判断する喜びこそが学びの真髄だからだ。子どもたちを触発する「複雑な問い」を、今日の教育事情に下いかに作問・指導するか。その方法・実例を具体的に示し、日本の授業の抜本的変革を現場教師に提言する。
目次
序章 学びのヴァーチャル化を排す(精気がない「ゲームの日常」;「学びもゲーム」をどうするか?;「ユニークな考えをもつ」ということ;「複雑な問い」の価値―テスト文化を変えるために)
第1章 学ぶに値することの現在位置(学ぶに値することとは何か;知識の構造化をめざす;学校単位のオリジナルカリキュラムづくりの時代に必要なこと;強い関心事をもとにオリジナル・カリキュラムをつくる)
第2章 「学ぶに値すること」の構造と設計(教科書との対応を示す;関連性を拾い出す;現実的な事柄に関心をもつ;日常生活のなかからの作問;公的資料・出版物からの作問;自己評価は学びの「鼓動」である)
第3章 考える問いをどう作るのか(なぜ課題の質を問うのか;本質的な課題をどう作るのか)
著者等紹介
小田勝己[オダカツミ]
城西国際大学非常勤講師。国立教育政策研究所研究委員
白鳥信義[シラトリノブヨシ]
栃木県河内町立古里中学校教頭。早稲田大学理工学部卒業後、栃木県の公立学校教員を経て現職。専門は理科教育。国立教育政策研究所研究委員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。