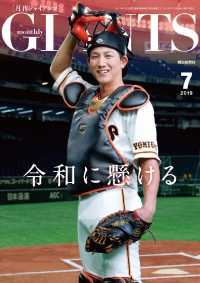出版社内容情報
『日本歴史』2012.11月号 評者:大豆生田 稔
本書は、近代日本において稲作に主体的に取り組んだ農民たちの営みを、「村に在って農事に精励し、村人を指導し牽引をしていく」在村の農事指導者たちに注目し、五つの地域の具体例に即して明らかにすることを課題としている。つまり、改良農法や新品種などの新たな技術が、実際に地域にどのように受け入れられ、さらに次世代に伝えられていくのかという問題意識である。そのキーワードは本書のタイトルにある「興農富村」であるが、これは「農業の興隆によって豊かな村を創」ること、すなわち、「興農」によりまず農家を豊かにしたうえで村を繁栄させることであり、それは富国につながるということを意味している。(略)さらに終章においては、五地域の検討を通じ、内在的な力を生む条件として、①複眼的視点をもつ指導者の存在、②基礎となる育種や種子交換などの営み、③青年会や農事小組合などの組織による次代への継承を指摘して、本書全体がまとめられる。本書に通底するのは、農村の「内在的な力」は、「寄生地主制」ないしは「金銭の出入りや土地の流出・集積などの経済動向だけ」では明らかにできないとする著者の基本的な姿勢である。このため、著者は在村の指導者にとどまらず、多くの人物を登場させて叙述をすすめている。農業や稲作にかかわる農民や地主、青年、町の商人、放浪遍歴の徒、さらには天皇、政府高官、府県知事、技術者たちの多様な思索や営為が考察の対象となっている。その多様な活動を、地域に即した多くの具体例によって丹念に叙述しているところが本書最大のメリットといえよう。特に、「関取」の伝播をめぐる多様な交流は、丹念なフィールドワークに支えられたものであり、興味深い。(略)本書が明らかにしたような、在村の指導者に支えられた農事改良の多面的な展開が、今後、地域の農業生産や農村社会の「経済動向」を解明する作業にも生かされていくことを期待したい。
『北日本新聞』『徳島新聞』『沖縄タイムズ』2012.1.22 「新刊紹介」より
明治以来、コメ増産を担い労働力を都市に提供し、兵士を送り出す源にもなってきた日本の農村には、災害や外米との競争にさらされながら、豊かな村づくりを目指す農事指導者たちがいた。明治~戦前期に北海道、埼玉、三重、鹿児島の稲作地で繰り広げられた「興農富村」の営みを検証し、農村が持つ内在的な力を解き明かそうとする本書。村の指導者らの情熱に触れると、日本農業の新たな相貌も見えてくる。震災復興、環太平洋連帯協定(TPP)を考える上でも示唆に富む
『北海道新聞』2012.1.29 「ほっかいどうの本」より
北海道における稲作の先駆者として知られる中山久蔵らの営みをもとに、近代日本の発展を根底から支えた農民や農村の力を考察する歴史論集
『図書新聞』2012.2.11 (3049号)より 評者:小林一穂
「興農富村」とはなんと魅力的な言葉だろうか。日本農業や農村社会の憂うべき状況に心を痛めることがしばしばである現在、この言葉の響きは、農業や農村が本来もっているものへの想いと、こうでなければという思いとを的確に表わしている。本書は、この表題を掲げて、明治期における日本社会の近代化のなかで、農業や農村の現場で、個々の農民がいかに農業の振興に努め、農村社会の発展に寄与したのかを、厖大な資料を駆使した緻密な文献実証によって明らかにした労作である。・・・略・・・それはともあれ、本書の最後に触れられいるように、育種にとどまらず、明治農法がどのように確立しどのように普及していったのか、またそうした農業技術の高度化に伴って、いわゆる農民教育が公私にわたってどのように展開したのか、今後の重要な論点となるだろう。さらなるけんきゅうの進展を大いに期待したい。
『地方史研究 NO.355』2012年2月 「新刊案内」より 評者:牛米 務
本書は、稲作を中心とする農民の主体的な営みを掘り起し、そこから近代日本の発展を根底で支えた農村の内在的な力を提示する意欲的な著作である。・・・略・・・本書には、興農富村の思いを胸に、資本主義発展の過程で、いくたびか訪れる危機のもと、時代と格闘した地域の青年たちの軌跡が描き出されている。・・・資本主義の発展に伴う経済危機のなかで、農村は、ともすれば脆弱で不安定な存在とされる。しかし、著者の眼差しは、一貫して地域の農民たちの主体的な活動に注がれ、興農富村を目指す農民たちの情熱や努力が、時代に適応した農業を発展させてきたことを描き出している。・・・略・・・昨今、TPPの加盟問題を巡って農業の崩壊が声高に叫ばれている。こうしたなか、時代の変化に対応して、新たな農業を切り開いてきた先人の主体的な取り組みを明らかにした本書から、私たちが学べることは少なくない。是非、ご一読をお勧めしたい。
目次
序章 課題と視点
第1章 開拓殖民と北海道稲作―中山久蔵の世界
第2章 種子島における農業改革―青年会と農事小組合の働き
第3章 興農富村への軌跡―埼玉県北川辺領の歩み
第4章 農家を支える営み―佐々木家と「関取米」
第5章 都市近郊の稲作農家―幸三郎家の半世紀
終章 成果と展望