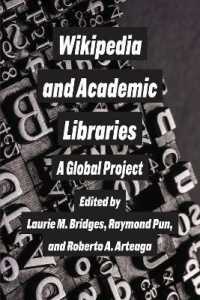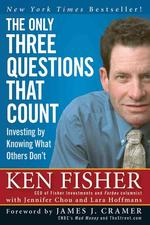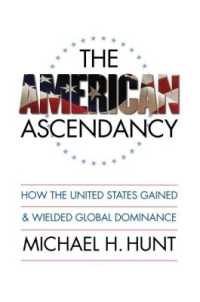出版社内容情報
「朝日新聞」書評(1979.12.2)
「インディアンの見た幕末の日本」という副題の通り、ペリーの率いる米艦隊の来航に先立つ1848年(嘉永元年)、数奇な生いたち、生来の冒険心を持った二十四歳の混血青年が北海道に密航、長崎に監禁された十カ月の見聞をつづった簡潔な記録である。十年後、最初の覚え書が書かれ、四十数年後、最終稿ができたが、一部が米地方紙に公表されただけで、刊行されたのは死後三十年を経た一九二三年(大正十二年)、邦訳は初めてである。長崎時代、森山榮之助ら十四人に英語を教えたことで「日本最初の英語教師」となり、明治年間、原稿を預かった友人マクラウドが朝日新聞社主村山龍平を森山の子孫と誤解して手紙を送ったことから、本紙(朝日新聞)に「懐旧の書簡」として当時、紹介された。(略)ハワイから捕鯨船に乗り組み、焼尻島沖で単身、ボートに三十六日分の食料、本と文具、四分儀などを積んで本船を離れた。無人の焼尻から利尻島を目ざし、遭難者とみせかけて救助され、アイヌ人の好意を受けた後、宗谷、松前を経て、北前船で長崎に護送されて寺に監禁される。この間の処遇、取り調べの模様、アイヌや日本人の風俗人情、求められて長崎通詞に七カ月、英語を教えた経過が淡々と述べられている。老人になって補訂したための誤りなどは訳注によってただされ、周到な解説が添えられている。彼の見た幕末の日本人は――生来おしゃべりでユーモアを解する。勇敢で死を恐れない。賢い国民であり、必要としているのは外からの光だけである。(略)いま日本人論が盛んだが、幕末、明治期に来日した外国人の見た日本見聞記を読み直してみることも一助になるだろう。百年前後のうちに、日本人の品性に何がプラスされ、マイナスされたかが分かるからである。
「対談:ことしの本 江國滋/永六輔」『波』(1983年12月号)
・永六輔談
毎年僕は読書について方針を立てるんだけど、本年度は、どこか一つの出版社の出版物を全部読んでみよう、という方針を立てたわけ。それで、お正月に本屋さんでリサーチをして、結局、出版社まるごとではないけれども東洋文庫(平凡社)を全部読んでみることにした。(中略)
・永六輔談 [今年のベスト3]
僕があげられるのは東洋文庫とのつながりで読むことになった本ばかりですけどね、最近読んで特に印象深かったのは、長崎で日本人にはじめて英語を教えたインディアンの酋長の回想録だな。幕末のペルリ来日の前に日本に漂着したマクドナルドというアメリカインディアンの酋長がいたんです。アメリカの人種差別に嫌気がさして、捕鯨船で日本の近くまでやってきて、日本を差別のない新天地と思って漂着した人物です。長崎に送られた後、すぐに追放されるんですが、追放までの期間、はじめて日本人の通詞に英語を教えたんです。このマクドナルドがもしいなかったら、ペルリが来たとき通詞は英語で話せなかったはずなんです。『マクドナルド「日本回想記」』という本ですが、時代考証の人たちは、テレビでいろいろ言っていますけれども、外国人の書いた日本の記録をもっともっと読むべきだと思いますね。(以下略)
日本をインディアンの母国と信じて密航した青年の日本観察記。混血青年を優しくあたたかく遇した幕末の日本と日本人の美質を評価。また幕末最初の英語教師として評価されて,高校英語教科書にものっている
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
本の蟲
印度 洋一郎
高木康宏