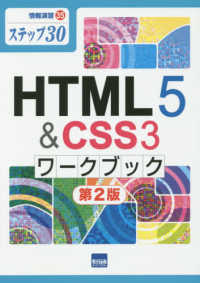内容説明
助け合う関係の歴史。共存の哲学。クロポトキンの思想は、過激でも奇矯でも夢物語でもない―。現代の環境危機を前に、持続可能な生命活動のために、「相互扶助」は人間と社会の再生をかけたキーワードだ。
目次
クロポトキン『相互扶助論』から学ぶ(相互扶助の成立;相互扶助の歴史 ほか)
相互扶助の暗黙知を再発見する―クロポトキンには見えたもの(相互扶助と自由な個;無意識の良心 ほか)
いまクロポトキン『相互扶助論』を読み直す―「新しい中世」の時代(ランダウアーとロマン主義的社会主義;アナ・ボル論争にたどり着く ほか)
あとがきにかえて 相互扶助の甦りを考える(パンデミックに対する「自衛」が変えるもの;地球規模の生物圏の「自衛」活動 ほか)
著者等紹介
大窪一志[オオクボカズシ]
1946年生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。編集者を経て著述業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ñori
3
クロポトキンの相互扶助論は、モースの贈与論に対をなす近代へのアンチテーゼである。無意識の良心は、贈与の無意識であり、国家の社会への埋めなおしは、経済の社会関係への埋め込みなのだ。つまり、現代において相互扶助は、過去への純粋回帰ではなく、より高い次元で倫理的回帰を要請している。それは柄谷氏の贈与の高次元の回復と全く同じ論理構造を持っている。なるほど、柄谷氏もプルードンを参照にするわけだ。本書はつながりきっていなかったシナプスを直列につないでくれた。課題は山積だが、清々しい読後感。2022/05/30
-

- 電子書籍
- 泣き虫鬼さん拾いました【マイクロ】(2…