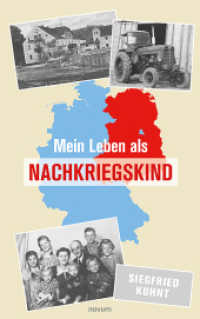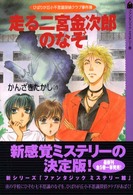内容説明
縄文時代を「定住により平等主義が動揺し始めた歴史段階」と捉えた著者は、永年追究してきた押型文土器研究の成果を駆使し、煙道付炉穴や土偶の新たな解釈にも触れつつ、緻密な分析から縄文社会の実相に迫る。
目次
第1部 近畿・中部地方における前半期の押型文土器(問題の所在と論述の前提;製作技法と型式要素の優先順位 ほか)
第2部 煙道付炉穴(研究史と問題の所在;分類と分布;復元・燃焼実験と小型化の理由;主軸方位と掘削事情と操業季節;堅果類とその利用法;炉の分類と煙道付炉穴の一義的な用途)
第3部 領域と生業システム(櫛田川流域から見た領域の問題;セトルメントのパターンとシステム;定住化の段階と備蓄革命;関係行動パターンと文化動態や領域)
第4部 前半期の土偶(前段階―研究史と問題の所在;第一段階―各部身体表現の事実確認;第二段階―各説の検討;第三段階―分類と土偶両性説・巫覡論)
第5部 定住による平等主義の動揺(平等主義と定住;平等主義の動揺した時代)
著者等紹介
山田猛[ヤマダタケシ]
1949年静岡県生まれ。2011年三重県教育委員会(社会教育・文化財保護室長)定年退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。