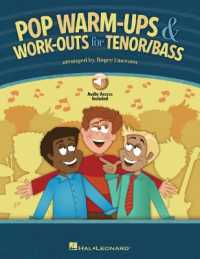内容説明
稲作伝来以来、わが国ではどのように水を田畑に引き入れてきたのか。流量変動が大きく急流な河川から安定して取水することは時代が遡るほど困難であったとする通説に疑義を呈し、最新の発掘成果と文献史料の分析を通して、古代日本の河川灌漑の実態を明らかにする。
目次
灌漑に関する研究史と本研究の視点
古代日本における「溝」の意味
史料にみる古代の河川灌漑の様相
井堰を祀る神社
桂川(京都市)流域の灌漑状況
岡山市津寺遺跡の大規模護岸施設の再検討
砂礫堆と湾曲斜め堰
発掘調査で検出された湾曲斜め堰
韓国における灌漑史研究―河川潅漑を中心に
中国大陸の歴史的水利施設
まとめと今後の研究の展望
著者等紹介
木下晴一[キノシタセイイチ]
1961年、東京都杉並区生まれ。同志社大学大学院文学研究科博士前期課程修了。1988年より香川県教育委員会職員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 復讐の女神 ハヤカワ文庫