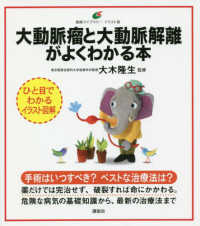目次
西南日本を行く(温泉都市指宿とカツオの町山川(指宿・山川)
道路と港の近代化だけが目立つ過疎の町(里・上甑) ほか)
中央日本を行く(変わり行く平等院とお茶の町(宇治)
道路・鉄道の分岐点の町(米原) ほか)
東京とその近郊を行く(東京ど真ん中の“地図の旅”(東京(千代田区、中央区))
江戸時代の宿場町から平成の宿場へ(東京(品川区)) ほか)
東北日本を行く(温泉の村と鉱山の村が合体して…(熱塩加納)
“本物志向”の観光都市に育ってほしい(会津若松) ほか)
著者等紹介
大沼一雄[オオヌマカズオ]
1923年生まれ。1950年東京高等師範学校地理学科(現筑波大)卒業。桐朋中・高等学校教諭をへて現在フリー、地図と旅の執筆活動に専心
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
19
○地図による変遷を確認しつつ、実視についてもありきたりでない大変興味深い紀行文です。いったことある場所は自分との感覚の違いを楽しめ、いっていない場所はいきたくなるところが増えました。地図がこれまた夢中になれます。都城、米原、金沢、岐阜、真壁、さいたま、根室が良かったです。2022/08/08
wei xian tiang
3
明治より四代の地形図を対照の上、実地に歩いてみる萌え書。今月のベスト萌えに認定。類書は世に色々あろうが、著者は一箇所に一週間近く滞在することもあり、また高度成長期前に自ら訪問した記録と対照したり、とにかく萌える。伝建や景勝に限らずこれということのない新道を数時間ひたすら歩いてまた戻って来るなど、きっと散歩の神が共にいるお人である。嘗ての相模大野は本当に一面の原野だし、米原の変遷、番場の谷道は小謡の海道下りを思い出しトリップしてしまう。地形図は読む麻薬。2014/12/18
-
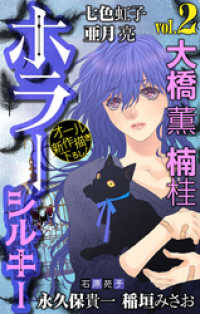
- 電子書籍
- ホラー シルキー Vol.2 ホラー …