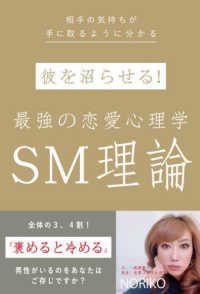内容説明
戦後30年以上経てもなお、アメリカ合衆国司法省特別調査員がかつての個人の戦争犯罪を追求する「二つのスーツケース」、キリスト教からユダヤ教に改宗したドイツ人女性ヴェロニカが、結婚前夜に夫になるウリヤに宛てた手紙「でも、音楽は守ってくれない」、イスラエル建国当時の世界各地に出自をもつ移民同士の距離感を子どもの目線で描く「ルル」、1942年の強制連行から約3年間の収容所生活とロシア軍による解放を綴った表題作「ガラスの帽子」など、9篇を収録。
著者等紹介
セメル,ナヴァ[セメル,ナヴァ] [Semel,Nava]
1954年、ホロコーストを生き延びた両親の元、イスラエルに生まれる。テルアビブ大学にて美術史のMAを修了後、ジャーナリスト、テレビ、ラジオのプロデューサーを経て作家になる。数多くの小説、詩集、脚本、児童書、YA作品は数か国語に翻訳され海外メディアで放送、上映、また舞台で上演される。イスラエル国内およびアメリカ、ドイツ、オーストリアの文学賞やドラマ賞を受賞。2017年没する
樋口範子[ヒグチノリコ]
1949年、東京生まれ。立教女学院高校卒業と同時にイスラエルに渡り、二年間キブツ・カブリのアボカド畑で働く。帰国後、山中湖畔にある児童養護施設の保育士、パン屋、喫茶店運営を経て、現在はヘブライ文学の翻訳をライフワークにしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buchipanda3
93
戦後、イスラエルで生まれた作家の短篇集。主に両親や祖父母の頃の話が描かれ、ホロコーストが残した記憶を語ると共に、それらが子や孫にどんな思いを伴って受け継がれているのかを感じさせるものがあった。感情的ではない文章だが挿まれる詩的な描写は深い心の情感を見せた。前代の悲しみは次代にも透明ながら存在感を持って覆いかぶさり続ける。血が記憶を浄化させない厳しさ。一方でかつての収容所の地は草で覆われる。大地は神の御心に。それは過去も。右手が殴られれば左手はどうだろう。著者から自然な敬虔さを感じた。お気に入りは「ルル」。2023/09/14
たま
59
イスラエルの作家ナヴァ・セメル(1954-2017)の短篇集。9つの短編はいずれも1人称で語られるが語り手の性別や世代はさまざまでイスラエルの社会が多面的に浮かび上がる仕掛けとなっている。大戦を挟んだ一家の離散と集合、強制収容所の経験、ドイツ人女性とイスラエル人男性の結婚の障壁、移民の子供の言葉の壁。。。中でも母が渡米して元ナチス党員を告発する「二つのスーツケース」はその息子の過敏な反応が彼の心の傷を示して印象深い。「ファイユームの肖像画」はググってミイラの肖像画の実に生き生きとした表現に驚かされた。2023/10/29
天の川
57
戦後生まれのイスラエルの女性作家による短編集。作家の祖父母の奇妙な愛憎劇を記した冒頭作から惹き込まれる。表題作の女子収容所での自らの身を捧げることで囚人達を守ったクラリサに心打たれ、ナチの犯罪を証言するためにアメリカに出かける両親を心配する息子の『2つのスーツケース』では今もなお続く恐怖と不信を知る。ユダヤ教に改宗し、イスラエルに嫁ごうとするドイツ人女性がどちらの社会からも拒絶を受けながらも新たな人生に踏み出そうとする『でも音楽は守ってくれない』が、戸惑いつつ手を差し伸べる母と義母も含めとても心に残った。2023/09/13
つちのこ
28
ホロコーストの悪夢は子や孫の世代にまで伝染し、遺恨を残し続ける。『ガラスの帽子』はそんな悪夢を脱ぐことのできない帽子に例えて、体の重要な一部とした比喩である。建国間がないイスラエルではホロコーストの生還者が歓迎されず、むしろ避けられ、虐げられていたという。「ホロコーストはなかった」のごとく、歴史の闇に葬むることはできない。生還者たちが忘れようとしても消し去ることができない悪夢は、時の隙間に入り込むように戦後何十年が経っても凶暴な姿となって現れてくる。収録された九篇は重く沈むような因果と捉えることが⇒2023/10/25
のんたろう
4
イスラエル女性作家が、ホロコースト生還者とその次世代の心の傷を描いた短編集。ガラスの帽子とは、ホロコースト生還者の子や孫が無意識のうちにまとわされ、脱ぎ去ることのできないもののたとえだそう。人の心は、戦争は終わりましたよ、今日からみんなハッピーに生きていけますよ、とはいかない。様々なかたちで心に残り続け、次の世代も逃れることはできない。イスラエルとパレスチナの情勢を思うと、痛みを知る人たちがなぜ、と複雑な思いも。知識が足りないせいで理解しきれないところもあるが、だからこそ読むことができてよかったと思う。2024/02/16