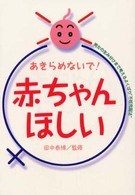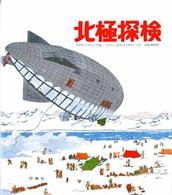内容説明
昭和4(1929)年3月、28歳の土方久功は、単身南洋パラオへ渡った。着いて3か月後、南洋庁の嘱託に採用され、島の子供たちが学ぶ公学校で木彫を教えた。その時の教え子は、後にパラオの民芸品「ストーリーボード」を制作し、今日まで受け継がれている。久功は、南洋に13年間滞在し、島の人々とともに暮らし、「日本のゴーギャン」と呼ばれた。彫刻の制作をするとともに、民族学調査を行った。久功は、関東大震災の前年から死の5日前まで55年に渡って日記を書き続けた。膨大な日記からは、自己に忠実に生きようとした姿が伺える。日記は、民族学のフィールドノートとして貴重であるとともに、丸木俊、中島敦との親交についても書かれている。
目次
第1章 幼年から青年時代へ
第2章 死の影
第3章 遥かなる南洋へ―パラオの生活
第4章 孤島に生きて
第5章 再びパラオへ―丸木俊と中島敦
第6章 戦時下の日本へ
第7章 ボルネオから土田村へ
第8章 戦後東京の生活
第9章 パラオ、サタワル島の人々との交流
終章 栄達、名誉を求めぬ一生
著者等紹介
清水久夫[シミズヒサオ]
1949年(昭和24)、東京に生まれる。法政大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得。日本学術振興会奨励研究員、法政大学非常勤講師を経て、世田谷区総務部美術館建設準備室学芸員となる。世田谷美術館開館後は、学芸部教育普及課長、資料調査課長等を勤める。元・埼玉大学・法政大学・跡見学園女子大学非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
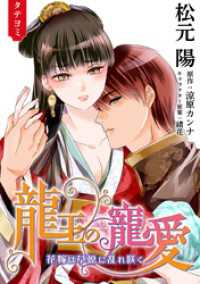
- 電子書籍
- 龍王の寵愛 花嫁は草原に乱れ咲く【タテ…
-
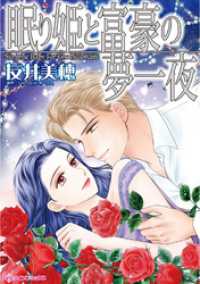
- 電子書籍
- 眠り姫と富豪の夢一夜【分冊】 9巻 ハ…