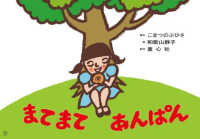目次
人格形成における空想の意味
昔話と子どもの空想
昔話における“先取り”の様式―子どもの文学としての昔話
お話に関する評論一覧―機関誌「こどもとしょかん」バックナンバーより
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
絵本専門士 おはなし会 芽ぶっく
10
初めていった街の図書館で、時間つぶしのつもりがすっかり夢中になってしまいました。地元や近郊にない本を読みあさりました(笑) 機関紙「こどもとしょかん」の評論と記事の三篇。自分たちが語る物語、語るという営みを学ぶ2021/12/02
joyjoy
8
小宮由氏の講演会で、昔話の「先取り」のことが載っていると紹介された一冊。先取りの様式についても興味深く読んだが、「人格形成における空想の意味」のなかの、無意識の話も面白かった。「お話を語っている人は、外側からは見えないけれども、やはり語ることによって、自分の内面と対決し、内面的な強さを養っていらっしゃるんじゃないでしょうか。昔話を語ることは、語り手の無意識とどこかでかかわりますからね。…」 「…われわれはお互いに知らないところで影響し合い、知らないところで、心の豊かさを育てているんじゃないか…」2024/10/15
Midori Matsuoka
8
昔話ってどうして子どもたちは好きなんだろう、想像力を育むために昔話や絵本・本を読むことが良しとされているけれどなんでなんだろう、そんな疑問への糸口になる評論3編をまとめたブックレット。昔話や子どもの本の研究をしている人におすすめ。 心理学者シャルロッテ・ビューラーによる『昔話と子どもの空想』は1918年の研究にも関わらず、系統立てや考察が全然古めかしくないことに感動してしまう。 更に松岡享子さんによる講演、小川捷之氏による講演内容で語ること、空想することの意味付けがしっかりとされていてとても勉強になった。2024/02/08
鳩羽
6
子どもの空想(具体的にイメージする力)に昔話がどういう働きかけをするのかについての3つの講演録、評論をまとめた一冊。読んだことあるなと思ったので、どこかでレポートの課題になってたのかも。昔話の視覚的な分かりやすさ、人物の内面が無いことが、単に分かりやすさのためだけでなく、子どもの内側にあるまだ未成熟な空想する力に働きかけ、推論したり、時間を遡って省みたりすることを促すのではないかということが説明されている。子どもへのお話が、面白いのは大前提としても、ウケればよいという訳ではないことがよくわかる。2021/03/27
rummy
0
「先取り」の力。 「かえるの王さま」「ルンペルシュティルツヘン」「いばらひめ」「赤鬼エティン」「三枚のお札」「なら梨とり」 大切に語りたい。2024/12/21
-
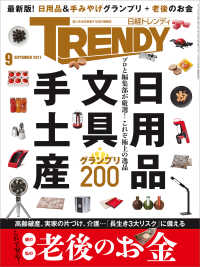
- 電子書籍
- 日経トレンディ 2017年 9月号
-
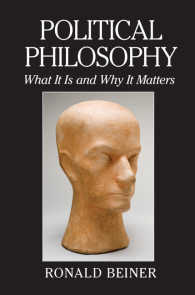
- 洋書電子書籍
-
政治哲学とは何か、なぜ重要なのか