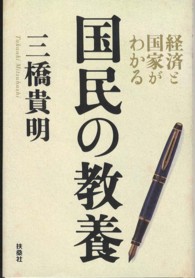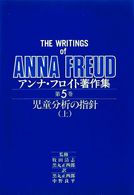内容説明
剣道教育者・指導者を養成する国際武道大学。その国武大の指導陣が一回の稽古を充実させるための秘訣をわかりやすく紹介。一本に直結する稽古はこうして行なう。
目次
これが効果的な稽古の方法だ―すべての稽古は一本を打つためにある
崩し方を学ぶ―実戦崩しの技術六種と十二の技
中心の取り方を学ぶ―構えと左手を連携させて中心を取る
突き攻めを学ぶ―突き稽古で会心の一本をつくる
攻め足、打ち足を学ぶ―足幅を常に意識して身体の軸を崩さない
しかけ技を学ぶ(一足一刀から打ち間に入るまでが勝負;動こうとした兆しをとらえる)
応じ技を学ぶ―剣先をゆるめて打突を引き出す
効果的な素振りを学ぶ―三段階の素振りで打突感覚を身につける
剣道百五十問百五十答
身になる稽古、身にならない稽古
著者等紹介
蒔田実[マキタミノル]
昭和23年大阪府生まれ。PL学園高校から東海大学に進み、卒業後は日本運送(現トールエクスプレスジャパン)に勤務。昭和59年の国際武道大学開学とともに同校の教員となる。世界剣道選手権大会個人優勝、全剣連設立50周年記念全日本選抜八段優勝大会準優勝。現在、国際武道大学学長。剣道教士八段
井島章[イジマアキラ]
昭和32年秋田県生まれ。本荘高校から日本体育大学に進み、同大学研究員を経て昭和59年の国際武道大学開学とともに同校の教員となる。全日本東西対抗剣道大会、全国教職員剣道大会出場。現在、国際武道大学教授、同大学剣道部長。剣道教士八段
丸橋利夫[マルバシトシオ]
昭和37年秋田県生まれ。秋田南高校から筑波大学に進み、卒業後、国際武道大学の教員となる。全国教職員剣道大会出場。現在、国際武道大学教授、同大学剣道部男子監督。剣道教士八段
岩切公治[イワキリキミハル]
昭和41年宮崎県生まれ。高千穂高校から国際武道大学に進み、卒業後、助手として大学に残り、後進の指導にあたる。全日本東西対抗剣道大会、全国教職員剣道大会出場。現在、国際武道大学准教授、同大学剣道部女子監督。剣道教士七段(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。