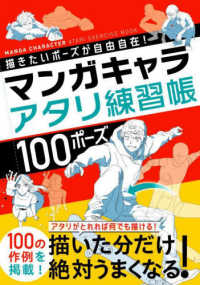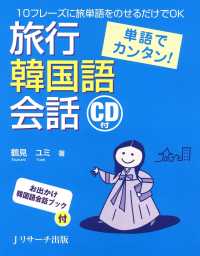出版社内容情報
アメリカ短篇小説の“名作中の名作”を直球で選んだアンソロジー、待望の第2弾!
【収録作品一覧】
●シャーウッド・アンダーソン「グロテスクなものたちの書」
●アーネスト・ヘミングウェイ「インディアン村」
●ゾラ・ニール・ハーストン「ハーレムの書」
●イーディス・ウォートン「ローマ熱」
●ウィリアム・サローヤン「心が高地にある男」
●デルモア・シュウォーツ「夢の中で責任が始まる」
●コーネル・ウールリッチ「三時」
●ウィリアム・フォークナー「納屋を焼く」
● F・スコット・フィッツジェラルド「失われた十年」
●ラルフ・エリスン「広場でのパーティ」
●ユードラ・ウェルティ「何度も歩いた道」
●ネルソン・オルグレン「分署長は悪い夢を見る」
内容説明
アメリカ合衆国で書かれた短篇小説、その“名作中の名作”を選ぶ。ヘミングウェイ、フォークナーなどの巨匠による「定番」から、ハーストン、ウェルティ、オルグレンの本邦初訳作まで。激動の時代、20世紀前半に執筆・発表された全12篇を収録。
著者等紹介
柴田元幸[シバタモトユキ]
1954年生まれ。米文学者、東京大学名誉教授、翻訳家。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウン、ブライアン・エヴンソンなどアメリカ現代作家を中心に翻訳多数。2017年、翻訳の業績により早稲田大学坪内逍遥大賞を受賞。現在、文芸誌『MONKEY』の編集長を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
buchipanda3
104
柴田さん編訳の米文学アンソロジー。今回は20世紀前半の短篇を収録。ヘミングウェイやフォークナーなどお馴染みの作家も初読みの作家もいて、文体もテーマも様々で面白く読めた。あえて共通なのは人間の姿だろうか。冒頭の「グロテスクなものたちの書」の人間をグロテスクにしたのは自分のものとした真理というのがどの篇も当てはまるように思えた。グロテスクもバラエティに富むが。既読(別訳あり)の「インディアン村」「ローマ熱」「納屋を焼く」はやはり良い。他ではサローヤンとウェルティ、ハーストンが好き。これら作家の他作品も読むぞ。2023/08/19
キムチ
71
時間を追って柴田氏が選書した秀作、純古典篇。ノーベル賞作家ヘミングウェイ、フォークナーとサローヤン、ウーリッチ、フィッツジェラルド、オルグレンら・・本邦初翻訳も入っている垂涎モノ12作。20C前半といや戦争の世紀であり、頭上を戦闘機が飛び交い、恐慌の影響もあった時間。アメリカの昏い空気。また、南北戦争後半世紀を経ても尚アフリカンアメリカンが受けていた残逆さは色濃かったと感じる。現代から100年前でしかないのに、作品の情景は惨さすら覚えるセピア色。特筆は「ハーレムの書」最も読み辛かった中身。さもあらん→2025/03/03
nobi
65
和暦なら大正8年〜昭和22年、国力を上げていったアメリカの主に貧しい人達登場の12作品。テレビも携帯もなく馬車か馬で移動した時代。古語とアニメ言葉の奇妙な混淆、囚人達との怒涛のボケツッコミ、罵声頻発と一見不釣り合いな理屈っぽい文体、そんな引き伸ばすかと思う刻一刻にも現実と非現実の合間に生きる老女にも情が移り、ニグロへのありえない仕打ちの中少年の反応に救われ、現代とは次元異なる幻、難産と想定外の結末、ローマの風景と似合わない謀り事、日々の食べ物に事欠いている中の笑い…光景も文体も違うのにいずれも存在感抜群。2025/10/13
まこみや
56
英語翻訳の第一人者が“準古典”として何を選ぶのだろうという興味から手に取った。以下、掲載順に一言感想を記す。1序:グロテスクへようこそ、2不条理な他者、3荘重軽薄なパロディ、4一矢による反転、5限りなき逸脱、6夢の中で見る夢、7外界の侵蝕、8重厚晦渋な世界、9夢の跡、10自虐的な排除、11交叉する他者、12断片化された混乱。『準古典』に選ばれた20世紀前半の米小説を大雑把に概観すれば、19世紀までの小説では客観的で確固としてあった他者(外界)が曖昧で不条理なものへと変容していく過程と言えるのかも知れない。2023/12/24
M H
27
この版元から出ている柴田さん訳は結構読んでるかも。目を惹く装丁に違わぬ内容。脳にスルッと入る訳文に身を任せてあっという間に読了、しそうだったけどフォークナーわかんない(泣)わかんなすぎてwikiでちょっと理解。我が家に眠る「ポータブル・フォークナー」どうしようね。超有名作家が多いせいかあとがき解説は簡潔。特に良かったのはアンダーソン、ヘミングウェイ、ウォートン、ウールリッチ、オルグレン。つまり良すぎる。2025/02/04