内容説明
大安と仏滅から冠婚葬祭の作法、結婚式やお葬式のマナー、七五三などの家族行事、さらには初詣や門松といった年中行事まで日本の美しい風習をイラストと文章でやさしく解説。
目次
第1章 日常生活のしきたり(大安と仏滅;暦の読み方 ほか)
第2章 冠婚葬祭のしきたり(結納の作法;結婚式 ほか)
第3章 家族行事のしきたり(戌の日・帯祝い;お宮参り ほか)
第4章 年中行事のしきたり(初詣の作法;門松・正月飾り ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぴょん
14
お作法がイラスト付きでわかりやすく。何故そのお作法があるのか意味を知ることができた。楽しくお勉強できる本でした。2016/04/06
大先生
9
(かつての)常識的なしきたり等をイラスト付きで簡潔に解説した本です。大人ならこの本に書かれている程度のことは知っていると思います。実践しているか否かは別ですが。ちなみに、私自身は、お中元・お歳暮などを贈ったことありません(汗)大学生が読むといいかもしれません。私は大学生の頃、ゼミの忘年会で教授を差し置いて上座に堂々と座っていたところを先輩に注意されました(苦笑)2024/10/20
ちはや
9
一般的なことが書いてある感じかな。おおっ!と目を見張るようなことは特になし。2016/08/19
ひさか
4
2013年5月彩図社刊。今風の考え方に沿った案内、ハウツー本。楽しいイラストとともに、勘どころをおさえた内容で、うまくまとめてある。索引がないのが、玉に瑕。重版もしているようなので今からでも追加できないかなと思う。2016/12/08
のり
3
恥ずかしながら、カレンダーの六曜は、先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口の順になっていること、赤口を「しゃっく/しゃっこう」と読むことを知りませんでした。年賀状の表題に、賀正、賀春、迎春を使うのは、目上の人には失礼にあたること。拝啓は「拝(つつしんで)+啓(申し上げる)」、敬具は「敬(つつしんで)+具(申し上げました)」、草々は「走り書きで失礼します」という意味。女性は頭語を使わず、結語に「かしこ」を用いるのが一般的。知らないマナーがまだまだいっぱいあることに気づかされました。2014/10/03
-
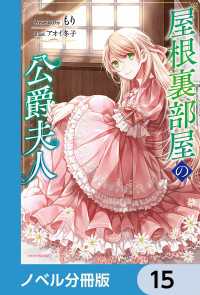
- 電子書籍
- 屋根裏部屋の公爵夫人【ノベル分冊版】 …
-

- 電子書籍
- 公爵令嬢の嗜み カドカワBOOKS






