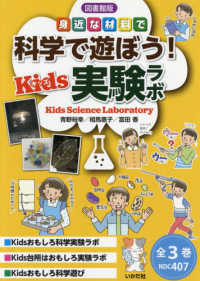内容説明
経済学のもっとも基本的な枠組みがまとめられたミクロ経済学について、そのごく初歩的前提から中級レヴェルの内容まで一気に説き明かし、刊行以来幅広く好評を得たテキスト、待望の改訂版!本書の特長はミクロ経済学における基礎的理論の解説を基本にしながら現実の経済問題を考察する際にもそうした理論が有効に適用できる可能性を示すことに重点を置いたところにあり、第2版ではこのようなアプローチをより明確にして、改訂を行った。まず理論の説明については、構成と記述を全面的に見直し、モデル分析の基本的な考え方に一層の理解が得られるよう、配慮した。数値例や図表を援用するというスタイルにも創意工夫をこらし、初学者でも直感的理解が得られるものとしている。さらにゲーム理論、情報の非対称性など、新たなミクロ経済学におけるテーマについても、内容の更新を図った。そして各理論と関連した、最近の日本経済の話題を数多く紹介して、リアリティをもってミクロ経済学が学べる本となっている。3色刷として体裁を一新し、いままでにない読みやすさ・わかりやすさを実現した、ミクロ経済学テキストの決定版。
目次
ミクロ経済学とは何か
需要と供給
消費の理論
消費理論の応用
企業と費用
生産の決定
市場と均衡
要素価格と所得分配
独占
ゲームの理論
寡占
外部性
不完全情報
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がっち
3
中級レベルのミクロ本。しかしミクロ経済に限っては他に良い本がいくつか出ているので、むしろ奥野さんを使うのがよいのではないかと思う。2012/08/01
えちぜんや よーた
1
著書の井堀先生はたまに経済誌でお見かけします。タイトルは「入門」ですが、ミクロ経済学の教科書や経済数学の本になれた中級の方におすすめかな?2010/12/22
葉
0
経済活動を生産・分配・支出の3つであることや、ミクロの流れをワルラスが定式化し、ヒックスによってGE化し、アローとドュブルーによって高度な数学へと進んで行ったと説明されている。アローの不可能性定理は集団の意思決定が完全に公平であっても合理的でないために投票制度が完璧ではないとしている。ゲーム理論は292頁からで、静学・動学の説明を戦略・展開型に分けて説明している。その後、不完全競争に進んでいる。2015/02/02
-
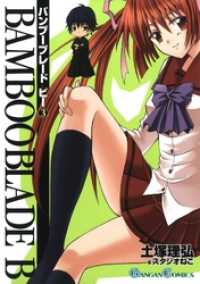
- 電子書籍
- BAMBOO BLADE B3巻 ガン…
-

- 和書
- 臨床気管支喘息