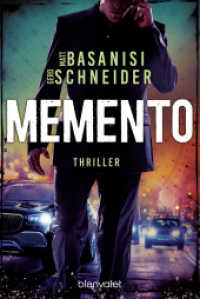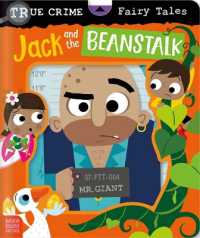出版社内容情報
《内容》 ●血管内皮細胞の機能とその破綻について、やさしく解説! ●臨床における各臓器ごとの治療戦略にも言及! ◆序文◆ 生命は40億年前に海中で誕生し、その後、36億年もの間、そこで維持された、海水のない環境の出現により、生命は、陸上生活を開始したが、生命の陸上での生活時間は、その歴史に10%に過ぎず、海と生命の関係は、いまだに密接であるといえる。ヒトにおいても、血管の中に閉じこめられた『豊穣な海』は、その生命維持にきわめて重要な関わりを有している。生体内に閉じこめられた『海』と常に接しているの細胞が、血管内皮細胞である。血管内皮細胞は、細胞社会から成り立っている『臓器という都市』のウォーターフロントに位置し、生命と海との重要な関わりを適切に保つことにより、各臓器の機能維持と臓器間の機能的統合において重要な役割を演じている。生体外部からの刺激は、神経系、および『海』の変化を介して体液系により細胞社会へ伝達される。血管内皮細胞は、この刺激を適切に制御して、臓器機能を維持する。過大な刺激(ストレス)に対しては、血管内皮細胞は、これに適応しようとするが(血管内皮細胞の活性化)、好中球の活性化とともに、これらの反応が過剰になると、その内なる海は荒れ狂い(微小循環障害)、これが、細胞社会の混乱(臓器機能不全)を招くことになる。すなわち、外敵に侵入(重症感染症)、内部組織の著しい崩壊(組織傷害)、さらに、著明な体液の損失や分布異常(ショック)などでは、これらのストレスに反応して、白血球が活性化される。この生体とストレスの『戦場』で、血管内皮細胞は、白血球から放出される本来は生体を防御するための炎症性メディエーターという『流れ弾』により、傷害を受けることになる。 重症患者管理において、このようなストレスの要因を取り除くことも重要であるが、同時に、血管内皮細胞と白血球の過剰な活性化を制御するような治療を施し、生体内の海の恒常性を取り戻すことも、臓器機能回復をはかるうえで、きわめて重要である。 本書は、月刊「集中治療」に連載された『血管内皮障害-その基礎と臨床』に一部加筆修正し、一冊の本にまとめたものである。本書では、血管内皮細胞機能とその破綻の機序について、各臓器ごとにかいせつし、最後に現在利用できる、またそして将来的に有用と思われる治療法について解説した。 《目次》 1 血管内皮細胞の機能とその破綻-オーバービュウ- 2 血管内皮の透過性制御機構とその破綻 3 血管内皮細胞による血流制御とその破綻 4 血管内皮細胞と炎症 5 血管内皮細胞の凝固線溶制御系とその破綻 6 血管内皮細胞と病態 胃粘膜傷害/肝傷害/ARDS/神経系 7 血管内皮細胞障害の薬物による治療
内容説明
本書は、血管内皮細胞機能とその破綻の機序について、各臓器ごとに解説し、最後に現在利用できる、そしてまた将来的に有用と思われる治療方法について解説したものである。
目次
1 血管内皮細胞の機能とその破綻―オーバービュウ
2 血管内皮の透過性制御機構とその破綻
3 血管内皮細胞による血流制御とその破綻
4 血管内皮細胞と炎症
5 血管内皮細胞の凝固線溶制御系とその破綻
6 血管内皮細胞障害と病態
7 血管内皮細胞障害の薬物による治療
-
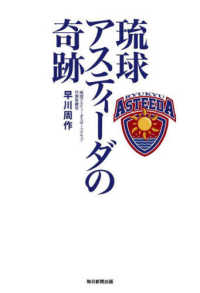
- 和書
- 琉球アスティーダの奇跡
-
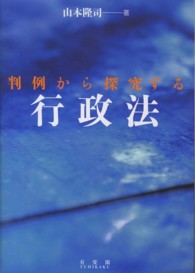
- 和書
- 判例から探究する行政法