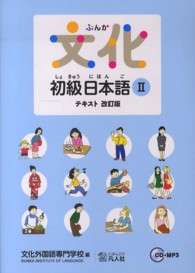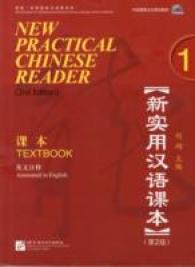- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学一般
目次
1編 古代知識の集積と図書館のはじまり(知識集積の形・知識の蓄積;ギリシャ思想と古代ローマの図書館;古代中国の図書館;インド・ラーナンダ大学図書館と仏教伝播;古代日本の図書館)
2編 中世社会の思想と図書館(宗教図書館と大学;宋・元代の図書館と中世日本の文庫)
3編 近世図書館思想の広がりとさまざまな図書館(ルネッサンスと図書館思想;近世日本の文庫活動;明の永楽大典と清の四庫全書)
4編 近・現代社会と図書館(近代社会と図書館;日本の近代化と図書館;20世紀の図書館;第二次世界大戦後の日本社会の動きと図書館)
著者等紹介
佃一可[ツクダカズヨシ]
1949、大阪府大阪市に生まれる。東京教育大学文学部卒業。横浜市文化財係長、横浜市瀬谷図書館長、横浜市中央図書館サービス課長、調査資料課長、神奈川県図書館協会企画委員長を歴任。現在、一般社団法人知識資源機構代表理事、公益財団法人税理士共栄会文化財団理事、中国法門寺(唐王朝菩提寺)博物館名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スイ
7
日本と外国の図書・図書館史を丁寧に解説していて、とてもわかりやすかった。 他の図書館史の本ではあまりページが割かれない中国や、ほとんど書かれないインド・イスラム圏などもしっかり書かれていて、読みごたえがある。 図書館史を踏まえてこれからの図書館を論じる最後のまとめには気迫と熱が感じられ、それもまた良かった。2018/09/20
スターライト
7
学校で習わなかった中国やイスラム世界の図書館史が含まれ、興味深く読んだ。特に中国が詳しく、始皇帝以前から現代までほぼとぎれなく系統的に紹介され、目からウロコ。ただ学校のテキストに比べて戦前の日本の図書館が、戦争に加担する道具とされた点を「時局に合わせて」などと表現され、随分ソフトな言い回しだと感じた。今後の図書館は、電子媒体の増加など情報技術の進展により大きな変化が予想されるが、紙の本はなくなることなく、これまでの図書館も存続すると信じたい。2015/07/09
CHARA
0
編集が良い。以前読んだ他の教科書よりはるかに分かりやすい。2013/10/12
わきが
0
色々な国の図書館の歴史が書かれています.図書館史から外れますが,民俗学者に支持されてできた公民館,満鉄資料が興味深かった.日本の第二次世界大戦後以降だけでもいいから年表ほしいです.2013/06/06
さちこ
0
復習にと思って読んだけど、時代ごとにそれぞれの国でどうなっていたかが分かるから、参考になった。2013/01/18
-
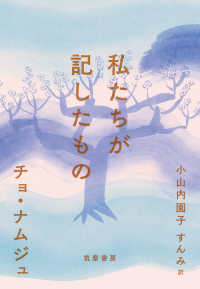
- 和書
- 私たちが記したもの