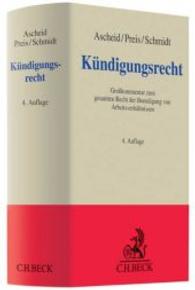内容説明
近代化とともに始まった鉄道の旅は、弁当とお茶を販売するという日本独自の駅弁文化を生み出した。実は、汽車土瓶と呼ばれたお茶の容器の多くは信楽で作り出されていたのだ。本書では、信楽汽車土瓶の歴史をたどるとともに、つくり手達にも目を向けることとする。
目次
写真でみる汽車土瓶の変遷
信楽汽車土瓶の時代(近代の信楽;信楽窯場における汽車土瓶の生産;信楽線と信楽窯場;汽車土瓶をつくる子ども達 信楽学園;汽車土瓶生産の裏方としての窯業試験場;信楽汽車土瓶の流通;信楽汽車土瓶の編年と製作技法)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
6
鉄道マニアも視野に入れるべき窯業の本。そして障害者福祉の本でもある。今やペットボトル化した駅弁用のお茶。昭和中期までは、土瓶に入れて売られていた。鉄道沿線の遺跡発掘で出土する遺物でもあるという。陶器の町・信楽はその主要生産地で、施設での生産教育として汽車土瓶を作り、障害者の生活や就職への基礎を育てていったことは、ぜひ記憶にとどめたい。小さな土瓶の歴史は、なかなかに大きいのだ。2013/12/22
やまほら
2
焼き物に特に興味があるわけではないので、「汽車土瓶」でなければ手にすることもなかった本だろう。当然、「汽車」よりも「土瓶」に関する内容が中心なのだが、何事も細かく調べるといろんなことがあるんだなあ、と興味深く読むことができた。ところで、土瓶と茶瓶は違うんですね。2012/02/21
-

- 電子書籍
- となりの魔王【分冊版】 20 Bs-L…