内容説明
日本列島の先住民であるアイヌ民族は、昔から自然と共生し、自然の知恵を学んで、素朴な生活をしながら、伝統文化をはぐくんできました。本書は、アイヌモシリ(大地)のうえで自然の恵みを享受して、自然とともに生きてきたアイヌ民族の生活文化を、わかりやすく説明したものです。
目次
ことば
ひとびとのあゆみ
えものをとる
よそおう
たべる
すまう
神々とひとびと
むらのしくみ
ひとの一生
うたとおどりと遊び
より深く学びたい人へ―参考文献や見学できる施設
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
びっぐすとん
18
図書館本。一番身近な異文化なのに何も知らないので夫が北の大地に赴任したのを契機に勉強。いつか博物館に行けるかもしれないし。初歩の初歩から言葉、衣食住、宗教観、一生のイベントなどを懇切丁寧に説明。明治期にもっとアイヌ文化に敬意を持っていたら、研究も保存も沢山出来ただろうに。自然と神と共に生きる生活は豊かだし、原始の人間の生活を垣間見れる。私の好きな『月神の統べる森で』のポイシュマの暮らしはアイヌの暮らしをモデルにしてるんだな。ずっと同じ列島で暮らしていたのに知らないことが多すぎる。トナカイはアイヌ語なのか。2019/12/24
ミネ吉
6
川越宗一さんの『熱源』を読んで感動し、アイヌ文化のことをもっと知りたくて、手に取ってみました。子供が読むことを想定しているためか、説明は平易で分量もほどほど。初めて学ぶ自分には丁度良い塩梅でした。章立ては「ことば」「ひとびとの歩み」「えものをとる」「よそおう」「たべる」「すまう」「神々とひとびと」「むらのしくみ」「ひとの一生」「うたとおどりと遊び」。素人目ながら、網羅性を重視しているように感じます。一番最後の「より深く学びたい人へ」で参考文献の紹介が丁寧にされており、読んでみたくなりました。2023/04/05
オクラちゃん
5
齋藤孝「読書する人だけがかどり着ける場所」から。 北海道にはなんとなく興味があったので読んでみた。 アイヌは文字をもたない民族であり、そのことが原因でアイヌの文化や民族そのものが正しく認知されていないことを学んだ。 北海道の地名には本州には無い独特の表現があり、それらがアイヌの言葉を語源としていることは知ってはいたが、そのあたりのことを学ぶのにも良い本だと思う。 アイヌの言葉を実際の音声で聞きたくなった。(初学しゃには文字では到底理解できない。) アイヌに限らず北海道のことをもう少し勉強したくなった。2020/08/31
noko
4
自分のある仮定を確かめる為読んだ。読んだ結果どうもその仮定は違っているみたいだとわかった。アイヌは文字を持たない。でもアイヌ語が由来なの、案外私も使ってる。シシャモ、ラッコはアイヌ語。この本は教科書的な本で、学生が読んでわかりやすい言葉使いで書いてあった。クマ送り(イオマンテ)についても復習。熊だけではなく他のものも送る。客人も送る。熊だけではではなく、フクロウも動物の中でも神様の扱い。水田はなかったけれど、畑はあって、雑穀などを育てていた。アイヌの家族構成は、一夫多妻だった。文字がないからこそ残したい。2025/07/10
ジュリ
4
アイヌの歴史、暮らし、食べものなどを、わかりやすくまとめてある本。ひとつひとつの項目はそれほど詳しくないけれど、大まかなことを知りたい人には役立つ。2022/11/10
-
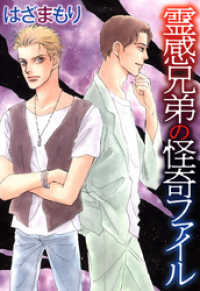
- 電子書籍
- 霊感兄弟の怪奇ファイル 青泉社




