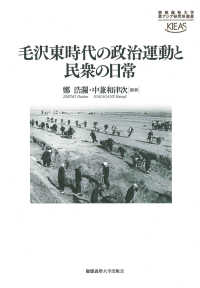出版社内容情報
甦る、樺太アイヌ語――浅井タケ(1902~94)という完璧な樺太アイヌ語の話者による、北辺の民・樺太アイヌ民族の貴重な昔話(TUYTAH)が見事に甦る!
樺太アイヌ語(ローマ字)と日本語訳を左右ページに対照並置。
【収録昔話】
1さらわれた娘(-84)2頭がい骨(-84)3カエルの話
4ポヌンカヨ(-86)5フンドシをとられた話
6ウンカヨお化け(-86)7アキアジの話8男探しの話
9水汲みの話10砥石男11カラスと娘12豊漁の神
13ヤチブキの話14ハシ細カラスとカラス15人食いババ
16魚の尾びれの話17丸顔スキー18ポヌンカヨ(-88)
19トンコリ娘20いびきの話(-88)21カニの話22さらわれた娘(-88)23箱流しの話(-88)24イムー女(-88)25フキとりの話(-88)26フグの話27おならの話28岩島に取り残された娘
29糸つむぎ(-88)30川上男と川下男31イムー女(-89)
32チツポ虫33ウェッターとコンブラ34頭がい骨(-89)
35ウンカヨお化け(-89)36いびきの話(-89)37フキとりの話(-89)38アザラシの胃袋39エチキーキ鳥40イムー女(-90)41腫れ物(-90)42頭がい骨(-90)43三人娘とウンカヨ
44スキー(-90)45踊りの話46牝イヌ47妾と本妻48箱流しの話(-91)49頭がい骨(-91)50盲目のイェース51スキー(-92)
52腫れ物(-92)53さらわれた娘(-92)54糸つむぎ(-92)
口述者/浅井タケさんのこと―――――――――――
浅井タケさん(1902~94、アイヌ名はTahkonanna タハコナンナ )は、1902年ライチシカより4キロほど南のオタスフ・コタンに山田チクユピ (Sahpo)を父にテツコ(Tekakunkemah) を母に生まれた。生後まもなく失明してから生涯、全盲だったが、実に耳の良い、素晴らしい記憶力をもった語りべだった。幼少の時両親に死別して叔母夫婦と共にライチシカに移り住み、北海道へ引揚げるまでいた。引揚げ後はしばらく夫と北海道日高地方の振内に住んでいたが、夫の死後は、最後の1年間札幌東病院に入院するまで、30年余りずっと日高門別の老人ホームに暮らしていた。タケさんは、長い間、アイヌ語を使わなかったにもかかわらず、1983年に編者が初めて会った時、アイヌ語を完璧に覚えていて、日常会話はもちろんのこと、昔話(TUYTAH)、民話(UCASKUMA)、神謡(OYNA)、歌謡(YUUKARA)など何でもできた。中でもタケさんが最も得意とするのは昔話(TUYTAH)であった。目が見えなかったタケさんの仕事はもっぱら子守りで、子守りをしながら語った昔話は、幼少の子どもから大人までみんなが聞きたがり大変な人気だったそうである。
甦る、樺太アイヌ語――浅井タケ口述
内容説明
浅井タケ(1902~94)という完璧な樺太アイヌ語の話者による、北辺の民・樺太アイヌ民族の貴重な昔話(TUYTAH)が見事に甦る樺太アイヌ語(ローマ字)と日本語訳を左右ページに対照並置。
目次
さらわれた娘
頭がい骨
カエルの話
ポヌンカヨ
フンドシを取られた話
ウンカヨお化け
アキアジの話
男探しの話
水汲みの話
砥石男〔ほか〕
著者等紹介
浅井タケ[アサイタケ]
1902~94。樺太アイヌ語の話者
村崎恭子[ムラサキキョウコ]
1960年、東京大学文学部卒業。北海道大学言語文化部教授を経て、現在、横浜国立大学教育人間科学部教授。『カラフトアイヌ語』(服部四郎と共編)1976年刊。『カラフトアイヌ語―文法編』(服部四郎と共編)1976刊
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。